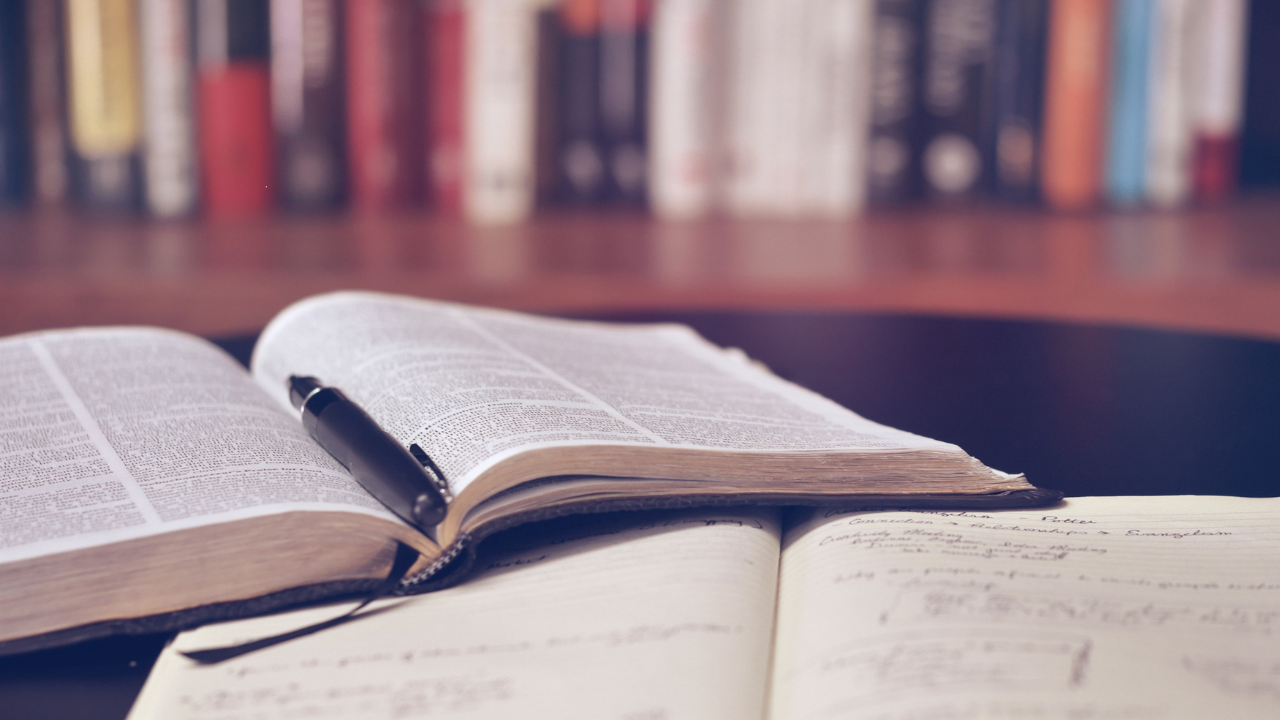更新日:2025年8月16日
投資に興味がない方でも、給与の受け取り先として、現金の保管場所として銀行口座はお持ちでしょう。
預金の特徴としては、ひとつの銀行につき1000万円までは元本保証でリスクなく
お金を貯めることができます。
しかし、日銀の金融緩和の影響もあり、預け入れ金利は低い状態が続いています。
金利が高い傾向にあるネット銀行でさえ0,02%~0,2%といった程度です。ちなみに普通預金の金利は0,02%程度です。
時折、「0,5%」といった破格の金利を提示する銀行がありますが、あくまでも1カ月間だけの期間限定キャンペーンなどです。
国債は国が発行する債券です。国がデフォルト、つまり債務不履行に陥らない限りは、
元本が保証され、半年に一度、利子を受け取ることができます。
国債の特徴
-
安全性が高い
- 国債は国が発行する債券であり、国の信用が担保となっています。
- 日本国債や米国債など、信用力の高い国の国債は「ほぼ無リスク資産」とみなされます。
- デフォルト(債務不履行)の可能性は非常に低いですが、ゼロではありません(例:アルゼンチンやロシアの債務不履行の歴史)。
-
利回りは低め
- 安全性の高さと引き換えに、リスクプレミアムが小さいため、株式や企業債券に比べて利回りは低め。
- 特に日本のように低金利政策が続く国では、利回りはほとんどゼロに近いこともあります。
-
満期まで保有すると元本は保証される
- 満期まで保有すれば、額面金額(元本)+利息が支払われます。
- 中途解約(市場で売却)すると、金利や市場環境により価格が変動する点には注意。
-
価格変動リスクがある
- 金利と価格は逆の関係にあります。
- 金利が上昇 → 既存の国債の価値は下落。
- 金利が低下 → 既存の国債の価値は上昇。
- 特に長期国債は金利変動の影響を受けやすいです。
-
流動性が高い
- 日本国債や米国債など主要国の国債は市場規模が大きく、売買も活発。
- ただし、新興国国債は流動性が低く、売りたいときにすぐに売れない場合があります。
-
インフレリスクがある
- 名目金利が低い場合、インフレ率が高くなると実質利回りはマイナスになることがあります。
- インフレに強い「物価連動国債」もあります。
-
分散投資の効果がある
- 株式などリスク資産と逆相関の動きをすることが多いため、ポートフォリオ全体のリスクを下げる効果があります。
- 特に株価が下落する局面では、国債価格が上昇しやすい傾向があります。
国債は「安全性が高く、資産を守る役割を持つ投資商品」
特に長期の資産運用では、リスク資産とのバランスをとるための安定資産として重要です。
個人向け国債を購入した場合、1%ほどの金利がつきます。
安全性については申し分ないですが、収益性については期待できません。
さらに高い金利を求めるなら会社が発行する「社債」や「既発債」、つまり、すでに発売されている債券を期間の途中から購入するという方法があります。
価格が下がっている債券は相対的に金利が上がるので、それを買うと多少お得に運用することができます。
既発債の価格は日々変動していますので、買い手は希望する利回り・投資期間に近いものを選んで購入します。
具体的には新発債(通常の国債)は個人向けであれば変動金利型(10年)、固定金利型(5年・3年)などがあります。いずれも最低金利は0,05%で保証されており、これよりも下がることはありません。
既発債は10年債の残り期間が7年になっていたり、5年債の残り期間が3年になっていたりします。
また金利が上昇する時は債券利回りが上昇し、債券価格は下落します。
金利が低下する時は債券利回りも下がり、債券価格は上昇します。
以上を踏まえて「最終利回り」を確認します。
最終利回りとは、既発債を購入した後、
保有者に額面金額を払い戻す償還日まで保有した時に、購入金額に対して、1年でどれくらいの収益を得られるかをパーセンテージで表したものです。
これは次の計算式で求めることができます。
国債の利回り計算
[利率+(償還単価−購入単価)÷残存期間(年)] ÷購入単価×100
たとえば表面利率0,05%、
購入単価99・95円、残存期間2年、償還単価100円だった場合、
[ 0.05+(100 −99.95) ÷2] ÷99.95×100 ≒0.075(%)
となり、利回りが上昇します。
まとまった資産で債券を購入する場合には既発債も選択肢に入れると良いでしょう。
著:株式会社FAMORE 代表取締役 武田拓也