会社員・公務員として毎月給与から天引きされる所得税・住民税。
額面上の年収が上がっても、手取りが思うように増えないと感じる人は多いのではないでしょうか。
実は会社員や公務員でも節税できる方法はいくつか存在します。
この記事では特に効果が高く人気のある「不動産投資」「ふるさと納税」「iDeCo(個人型確定拠出年金)」の3つに焦点を当てて仕組みやメリット、注意点をわかりやすく解説します。
1. 【節税の基本】会社員でもできる「控除」と「所得の分散」
まず押さえておきたいのは節税の仕組みについてです。
日本の所得税は「累進課税制度」が採用されており、所得が高くなるほど税率が上がる仕組みです。
つまり、節税とは「課税対象となる所得を減らすこと」です。
その方法には以下の2つがあります。
-
控除を活用する(所得控除・税額控除など)
例:ふるさと納税、iDeCo、扶養控除、医療費控除など -
経費や損益通算で所得を減らす
例:不動産投資、副業など
この2つを組み合わせることで会社員や公務員でも年間数十万円単位で税金を軽減することが可能です。
2. 【不動産投資による節税効果】「損益通算」で所得税・住民税を軽減
● 仕組み:赤字を給与所得と相殺できる
会社員や公務員が区分マンションやアパートを購入して賃貸運営を行うと家賃収入が得られます。
一方で減価償却費やローン利息、管理費などの経費が発生します。
これらを差し引いて帳簿上赤字になれば、その赤字分を給与所得と「損益通算」することが可能です。
たとえば、年間の家賃収入が100万円、経費が150万円であれば50万円の赤字になります。
この赤字がそのまま給与所得から差し引かれて所得税と住民税が軽減されます。
● 節税額の目安
所得税・住民税の合計税率が30%の人なら、50万円の損益通算で約15万円の節税効果が見込めます。
さらに、ローン完済後は家賃収入が安定的な「不労所得」として残るため、将来の資産形成にもつながります。
● 注意点
節税を目的にしすぎると、「キャッシュフローがマイナスなのに節税できた」と錯覚するケースもあります。
不動産投資はあくまで「資産形成+税負担軽減」を両立させる戦略であり、立地・利回り・融資条件を慎重に見極めることが重要です。
3. 【ふるさと納税】実質2,000円で地域を応援&節税
● 仕組み:寄附金控除で税金が戻る
ふるさと納税とは、自治体に寄附を行うと寄附額のうち2,000円を除いた金額が所得税・住民税から控除される制度です。
しかも、寄附した自治体からは特産品(お米・お肉・果物など)の「返礼品」も受け取れます。
たとえば、年収800万円の会社員が6万円寄附した場合、2,000円を除いた58,000円分が控除対象になります。
翌年の税金が軽減されるとともに、返礼品が実質2,000円で手に入る計算です。
● ワンストップ特例制度で簡単手続き
確定申告が不要な会社員や公務員は「ワンストップ特例制度」を使えば寄附先が5自治体以内なら申請書を送るだけで完結します。
ふるさと納税サイト(さとふる、楽天ふるさと納税、ふるなびなど)を活用すればクレジットカード決済などで簡単に申し込み可能です。
● 注意点
年収や家族構成により控除上限額が異なります。
限度額を超えて寄附しても控除されないため事前にシミュレーターで確認するのがポイントです。
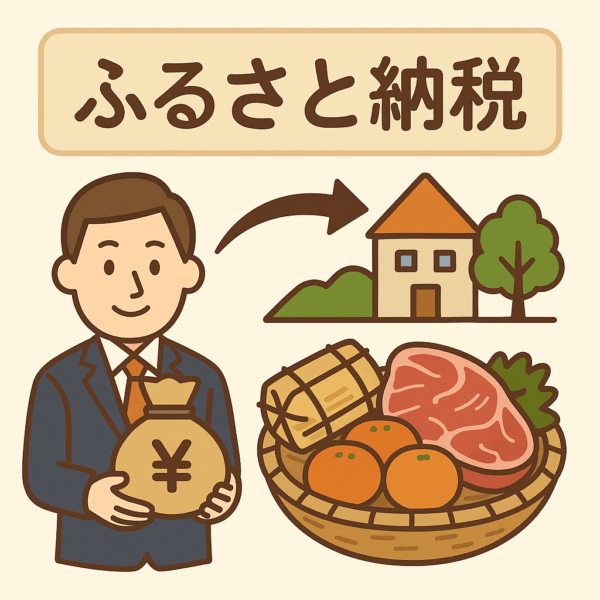
4.【 iDeCo(個人型確定拠出年金)】老後資金を貯めながら節税
● 仕組み:3つの税制優遇で効率よく節税
iDeCoは老後の資産形成を目的とした制度で、拠出した掛金がすべて「所得控除」の対象になります。
たとえば毎月2万円(年間24万円)を拠出した場合、所得税率20%・住民税10%なら年間約7.2万円の節税効果が得られます。
さらにiDeCoには3つの税制優遇があります。
-
拠出時:掛金が全額所得控除
-
運用時:運用益が非課税
-
受取時:退職金として受け取る際には退職金控除の対象
つまり拠出から受取までトリプルで税優遇が受けられる制度です。
● iDeCoのメリットとデメリット
-
メリット
✔ 掛金が全額控除されるため、所得税・住民税が軽減
✔ 運用益が非課税で分配金がないため複利効果が高まる
✔ 自動積立で資産形成の習慣が身につく -
デメリット
✔ 原則60歳まで引き出せない
✔ 商品選びによっては元本割れのリスクあり
節税効果を最大化するには低コストのインデックス型投資信託を選ぶのが基本です。
5. 3つを組み合わせた「節税戦略」
上記3つの方法は併用することでより高い節税効果を発揮します。
| 節税方法 | 節税の仕組み | 特徴 | |
|---|---|---|---|
| 不動産投資 | 損益通算で給与所得を圧縮 | 資産形成+節税の両立が可能 | |
| ふるさと納税 | 寄附金控除で税額軽減 | 実質2,000円で返礼品 | |
| iDeCo | 掛金が全額所得控除 | 老後資金準備と節税を同時に |
これらをバランスよく活用することで年収の高い人は毎年10万〜30万円以上の節税+将来資産形成が現実的に狙えます。
6. 節税で得たお金を「投資」に回す発想を
節税はゴールではなく、「可処分所得を増やすための手段」です。
節税で浮いたお金をそのまま消費に回すのではなく、投資信託・不動産・株式などに再投資すれば資産が加速度的に増えていきます。
特にiDeCoやNISAなどは税制優遇と複利効果の両方を享受できる王道の資産形成手段です。
7. 【まとめ】会社員・公務員でもできる「節税」で手取りを増やす
-
節税の基本は「課税所得を減らす」こと
-
不動産投資で損益通算し、所得税・住民税を軽減
-
ふるさと納税で地域を応援してお得に返礼品を得る
-
iDeCoで老後資金を積み立てながら所得控除
-
節税+資産運用で手取りを増やし、将来の安心を確保する
会社員や公務員であっても、これらを正しく理解し実践することで税負担を減らしながら豊かな人生設計を描くことが可能です。
「働いても手取りが増えない」と感じている人こそ、今日から節税と資産形成を始めてみてください。


