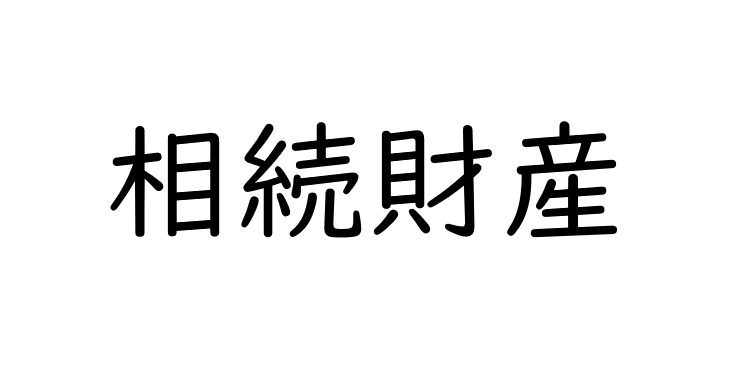相続は「財産を分けるだけ」と思われがちですが、実際には家族や親族の関係を壊してしまう深刻なトラブルに発展することがあります。
近年はこうした争いを「争族(そうぞく)」と呼び、誰の身にも起こり得る問題として注目されています。
遺言書がない場合や不公平感のある分配、生前贈与や不動産の扱いなど、典型的なトラブルには共通点があります。
本記事では、よくある相続トラブルの事例と防ぐための具体的な対策を解説します。
① 争族(そうぞく)とは?相続トラブルが起こる理由
「争族(そうぞく)」とは、本来は財産を円滑に引き継ぐための「相続」が、かえって家族や親族の間で争いを生んでしまう状況を指す言葉です。
表記上は「相続」の「相」が「争い」の「争」に置き換わっており、その名の通り相続にまつわるトラブルの象徴的な呼び方になっています。
相続は誰にでも発生する可能性がある一方で、準備不足や情報不足のまま進めてしまうと、思わぬ対立が表面化してしまいます。
特に「遺言書が存在しない」「財産の分け方が不明確」「生前の贈与や介護の負担が考慮されていない」などの要因は、争族の火種となることが多いです。
家族間での不満や不信感が蓄積すると、財産の価値そのものよりも「納得できない」という感情が争いの中心になるケースも珍しくありません。
つまり争族は、法律的な問題だけでなく、家族の関係性や心情が深く絡み合ったトラブルだと言えます。
② よくある相続トラブル事例
実際の相続では、さまざまなトラブルが発生しています。
典型例としてまず挙げられるのが「遺言書がないケース」です。
被相続人が遺言を残さずに亡くなった場合、相続は法律上のルール(法定相続分)に従って進みます。
しかし、財産をどう分けるかの解釈をめぐって意見が対立し、話し合いが長引いたり、家庭裁判所での調停や訴訟に発展したりすることも少なくありません。
また、遺言があったとしても内容が曖昧だったり、自筆証書遺言が形式不備で無効になったりする場合もトラブルの原因です。
さらに「長男に自宅を残す」「一部の子どもだけに多く与える」といった不公平感のある分配は、相続人間の不満を招きやすく、遺留分侵害請求につながることもあります。
近年増えているのは「不動産の分割」をめぐる争いで、分けにくい土地や住宅の扱いが大きな火種になります。
こうした事例からわかるのは、争族は財産の規模にかかわらず、準備や配慮の欠如で誰にでも起こり得るということです。
③ 争族が起こりやすい状況
争族が特に起こりやすいのは、特定の状況が重なったときです。
たとえば「生前贈与の偏り」や「介護の負担の不均衡」は典型的です。
兄弟姉妹のうち一人が多額の資金援助を受けていたり、同居して親の介護をしてきたにもかかわらず相続で考慮されない場合、不満が噴出します。
また「不動産が相続財産の大部分を占める」ケースも要注意です。
不動産は分割が難しく、誰が住み続けるのか、売却して現金にするのかで揉めることが多いです。
さらに、再婚家庭や内縁関係など、相続人が複雑化している家庭では感情的な対立が激しくなりやすい傾向にあります。
例えば「再婚相手と前妻の子ども」が相続人として混在するケースでは、法律上の権利が絡み合い、協議がまとまりにくいのです。
加えて、もともと兄弟仲が良くない場合には、相続をきっかけに過去のしこりが再燃し、財産以上に「感情の清算」が争点になることもあります。
争族は「財産の大きさ」よりも「状況と人間関係」に左右されるのです。
④ 争族を防ぐための具体的な対策
争族を防ぐための最も有効な手段は、被相続人が元気なうちから準備を進めることです。
第一に重要なのは「遺言書の作成」です。
財産の分け方を明確にしておくことで、相続人同士の解釈の余地を減らし、トラブルを未然に防ぐことができます。
特に「公正証書遺言」を利用すれば、形式不備による無効のリスクもなく、法的効力が確実です。
次に「生前贈与」の活用があります。
住宅取得資金や教育資金の特例を活用すれば税負担を抑えつつ財産を前渡しでき、後の不公平感を軽減できます。
ただし一部の人に偏ると逆効果になるため注意が必要です。
さらに「財産の見える化」も欠かせません。
預金や株式、不動産の一覧を整理し、家族と共有するだけでも不信感は大きく減ります。
最後に「生命保険の活用」も有効です。
不動産中心の遺産の場合、現金が不足して分割が困難になりますが、生命保険で現金を用意しておけば、公平感を保ちやすくなります。
これらを組み合わせることで、争族を未然に防ぐ準備が整うのです。
⑤ 家族間でできる工夫と専門家の活用
争族を避けるには、財産を整理するだけでは不十分です。
家族間の「納得感」をいかに得るかが重要です。
そのためには、本人が生前のうちに家族と率直に話し合う「家族会議」を設けることが効果的です。
「なぜ長男に自宅を残すのか」「介護を担った長女に多めに分けたい理由は何か」といった背景を説明すれば、相続人は決定に理解を示しやすくなります。
とはいえ感情が絡む話し合いは難しいものです。
そんなときには専門家の力を借りるのが得策です。
弁護士は法的な有効性を担保し、税理士は相続税や贈与税の負担を最適化します。
司法書士は登記や遺言執行を円滑に行い、ファイナンシャルプランナーは資産全体を見渡した上で将来のライフプランを踏まえた提案が可能です。
第三者である専門家を早めに関与させれば、家族同士が感情的にぶつかる前に冷静で合理的な解決策を導けます。
つまり「家族での合意形成+専門家のサポート」という二本柱こそが、争族を回避する最大の工夫といえるのです。
⑥ 争族を防ぐカギは「準備と共有」
相続は本来、家族の大切な財産を円滑に引き継ぐための制度です。
しかし、準備不足や不公平感が積み重なると「争族」と呼ばれる深刻なトラブルへと発展してしまいます。
実際に相続トラブルで家庭裁判所に持ち込まれる件数は年々増加しており、その多くは「遺言書がない」「不動産の分割が難しい」「生前贈与や介護負担への不満」など、事前に対策していれば避けられたケースです。
争族を防ぐためのカギは以下の4点です。
①本人の意思を明確に示す遺言書の作成
②財産の整理と「見える化」
③生前からの家族会議による情報共有
④専門家を早めに巻き込むこと
さらに、生命保険や生前贈与をうまく活用すれば、分割の難しさや不公平感を和らげることも可能です。
相続は「いつかやればいい」と後回しにされがちですが、早めに準備するほどリスクは減り、家族の安心につながります。
大切なのは財産を残すことよりも、「争いを残さないこと」。
それこそが本当の意味での“円満相続”への第一歩なのです。
【争族の原因6選】
-
遺言書がない、または曖昧な場合
被相続人(亡くなった方)が遺言を残さずに亡くなると、法定相続分に従って相続が進みます。
財産の分け方について相続人同士で意見が割れ、長期の話し合い・裁判に発展することがあります。
また、「自筆証書遺言」が形式不備で無効になった場合や、記載が曖昧だった場合もトラブルになりやすいです。
-
遺産の分け方に不公平感がある場合
「長男に自宅を残す」「一部の子どもだけに多く渡す」など、相続人間で差があると不満が生じます。
法定相続分と大きく異なる配分があると「遺留分侵害」として請求され、争いに発展することもあります。
-
生前贈与や介護の負担に対する不満
「生前に兄だけが多額の援助を受けていた」
「同居して介護をしてきたのに、その努力が考慮されていない」
こうした不満が表面化し、他の相続人と対立するケースが多いです。
-
不動産の相続で揉めるケース
遺産が「自宅」や「土地」といった分割しづらい資産の場合、誰が所有するかでもめやすいです。
特に、相続人の一人が住んでいる家をどうするかが争点になりやすく、売却・共有・分筆などで意見が割れます。
-
内縁関係や再婚家庭でのトラブル
「再婚相手と前妻の子ども」で相続人が複数に分かれるケースでは対立が激しくなりがちです。
内縁の妻(法律婚していない配偶者)や養子の権利関係も絡み、感情面での対立が深刻化する場合があります。
-
相続人同士の人間関係の悪化
もともと兄弟仲や親族関係が良くない場合、相続をきっかけに対立が表面化します。
「財産の多少」よりも「昔からのわだかまり」が原因で争いになることも多いです。
【争族を防ぐための対策6選】
-
遺言書の作成
被相続人の意思を明確に示すことで、相続人同士の無用な争いを防げます。
特に、財産の分け方に差をつけたい場合や、特定の人に多く残したい場合は必須です。
公正証書遺言(公証役場で作成)は形式不備の心配が少なく、安全性が高い制度です。
-
生前贈与の活用
相続開始前に一部の財産を生前贈与することで、相続財産を減らし、争いの種を減らせます。
「住宅取得資金の贈与」や「教育資金贈与の特例」など、税制上の優遇措置も活用できます。
ただし、贈与税の負担や「特定の人だけが得をしている」といった不公平感を生まないように注意が必要です。
-
財産内容の整理と見える化
財産がどこにどれだけあるのか不明確だと、不信感や疑念が生まれやすいです。
預金・株式・不動産などの資産を一覧にして整理し、家族に伝えておくと安心です。
不動産については「誰が使うのか」「売却するのか」を事前に方針を固めておくと良いです。
-
相続人への説明・家族会議
本人が元気なうちに、家族と話し合いの場を持っておくことが効果的です。
「なぜ長男に自宅を渡すのか」「介護に尽くしてくれたから長女に多めに残す」など理由を伝えると、納得感が高まり争いが減ります。
話しにくい場合は、弁護士や司法書士、税理士などの専門家を交えて「家族会議」を開く方法もあります。
-
専門家の活用
弁護士:法的トラブルを未然に防ぎ、遺言内容の有効性を担保。
税理士:相続税対策や生前贈与の節税スキームを検討。
司法書士:遺言執行や登記手続きをスムーズに進める。
ファイナンシャルプランナー(FP):資産全体の分配やライフプランを踏まえた提案が可能。
→ 専門家を早めに入れることで、家族が感情的に対立する前に合理的な解決策を導けます。
-
保険の活用
「現金が少なく不動産が多い」家庭では、分けにくさがトラブルの原因になります。
生命保険を活用すれば、現金を受取人に直接渡せるため、相続人間の公平感を保ちやすいです。