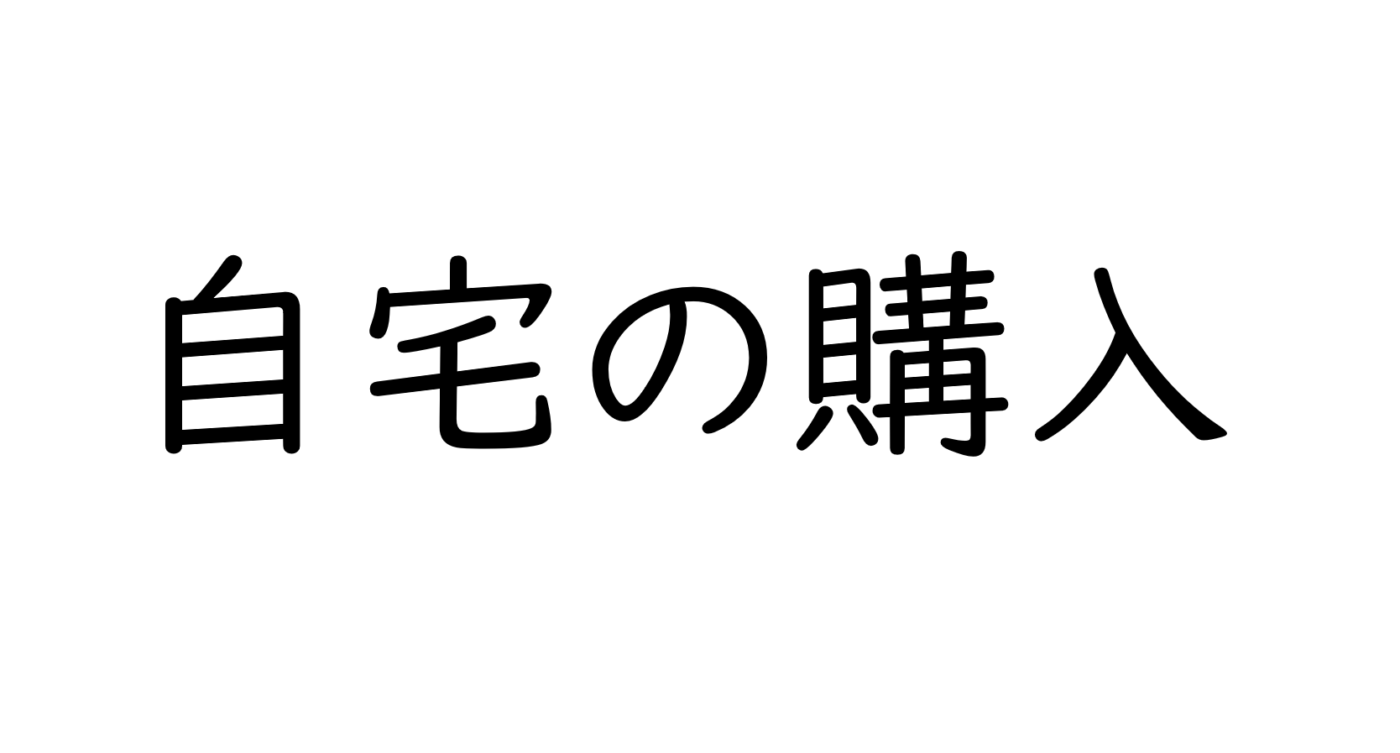インフレにより住宅の購入価格が上昇しています。
憧れのマイホームを購入したいと思っても長期の住宅ローンは負担が重く
なかなか自宅の購入に踏み切れないという方もいます。
その住宅ローンの負担を軽減する方法の1つとして「賃貸併用住宅」があります。
その賃貸併用住宅について分かりやすく整理します。
賃貸併用住宅とは
自宅の一部を賃貸として貸し出す住宅のことです。
自宅の50%未満の面積をワンルームなどとして貸すことで、賃貸収入を得ることができます。
例えば1階を自宅、2階をアパートとして賃貸に出します。
1階は自分たち家族が暮らす3LDK、2階は1Kを3室の間取りで建てたとします。
1室(1K)あたり月7万円の家賃を得られれば、3室で月21万円の収入が得られるので
住宅ローンの負担が大幅に軽減できます。
仮に7500万円の住宅ローンを35年間、1%で組んだ場合は月々のローン返済額は約21万円ですので
実質負担はほぼゼロになります。
賃貸併用住宅のメリット
①住宅ローンの軽減
・賃料収入でローン返済の一部をまかなえる。
・銀行によっては「住宅ローン」として低金利で借りられる。
②資産形成
・家賃収入を得ながら不動産(自宅)を保有できる。
・将来的に自宅部分を賃貸化して、完全な投資物件に転用することも可能。
③相続・節税対策
・賃貸部分は「貸家」として評価額が下がり、相続税対策になる。
④将来のライフプランに柔軟
・将来、収益物件として売却することにより住み替えをすることが可能。
賃貸併用住宅のデメリット・注意点
⑤入居者トラブル
・自宅と賃貸部分が近いので、騒音・生活習慣の違いなどのトラブルが起こる可能性がある。
そのため、間取りは専門家に作成してもらうのが安心。
⑥空室リスク
・入居者が見つからないと、賃料収入を見込めずローン返済に負担がかかる。
⑦プライバシーの確保
・賃貸部分と自宅の動線・音の遮断など、設計を工夫しないとストレスになる。
⑧初期費用が高い
・通常の住宅より建築コストが高く、収支計画をきちんと立てる必要がある。
そのため、現在の世帯年収で賃貸併用住宅の建築をできるのか判断が必要です。
賃貸併用住宅が向いている人
・将来的に住宅ローン負担を減らしたい人
・不動産投資に興味があるが、いきなり投資用物件を購入するのが不安な人
・将来、住み替えを考えている人
・相続対策を考えている人
賃貸併用住宅での成功ポイント
・駅近など立地条件の良い場所を選ぶ
・賃貸部分はその地域で需要のある間取りにする
・設計段階で自宅と賃貸部分で音が響かない間取りにする(水回りやクローゼット)
・収支シミュレーションを事前に行う(空室率・修繕費も考慮)
賃貸併用住宅は「マイホーム」と「投資用物件」の両面を持つため、
建てる際には通常の住宅以上に注意する必要があります。
以下に整理しました。
賃貸併用住宅を建てる際の注意点
①立地の選定
賃貸部分を貸すことが前提なので、賃貸需要のあるエリアで建てることが最重要です。
・駅からの距離(徒歩10分以内が理想)
・大学や会社の近く
・商業施設があるなど生活の利便性が良い場所
「自分が住みたい場所」と「借り手が探している場所」が一致するとは限らないので要注意。
②ローン・資金計画
・銀行によっては「住宅ローン」として借りられる場合と、「アパートローン(投資用ローン)」になる場合がある。
→ 金利や借入条件が大きく変わるため注意。
・空室リスクを考慮して、貯蓄をしておく。
・固定資産税や修繕費、管理費などのランニングコストを忘れない。
③設計・間取り
・自宅と賃貸部分の独立性を確保するのがポイントです。
・音や振動対策(壁の厚み、床の防音材)
・動線が交わらないようにする
賃貸部分は「貸しやすい間取り(ワンルーム・1LDK)」にする。
将来のライフプラン(子供の独立や住み替え等)を想定した設計にしておく。
④管理体制
・自宅に住みながら貸す場合でも、プロの賃貸管理会社に委託するのがおすすめです。
家賃の5%程度で家賃回収、入居者募集、トラブル対応を代行してくれます。
・自分で対応すると、生活にストレスが溜まりやすい。
⑤税務・法律面
・賃貸収入があるため、確定申告が必要。
・経費として計上できるもの(ローン利息・減価償却費・修繕費など)を把握しておく。
・将来、相続時には「貸家」として土地評価額が下がるメリットがあります。
確定申告と合わせて税理士など専門家に確認しておくと安心です。
⑥出口戦略
・将来、自分が住まなくなった場合には全室を賃貸化して投資物件化できるか?
・子供に相続させる場合に、管理できるか?売却できるか?
・「売る・貸す・住む」の選択肢を持てるようにしておくことが大事。
まとめ
賃貸併用住宅を建てる際の最大のポイントは
「自宅の快適さ」と「投資物件としての収益性」を両立させること」 です。
そのため、賃貸併用住宅を選択される際には専門家に相談することをお勧めします。
ノウハウのない専門家や不動産会社に頼むと後々のトラブルが絶えませんので注意してください。