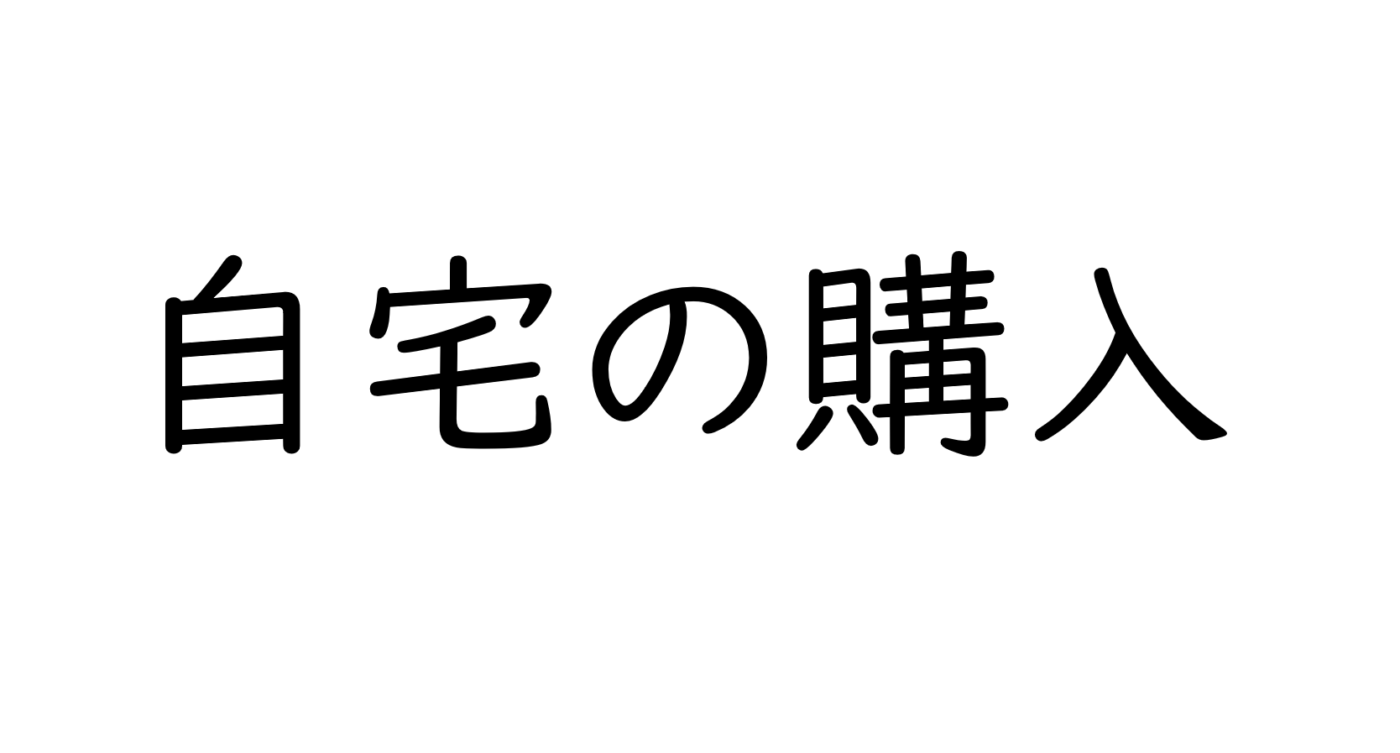コロナ以降、インフレが加速して住宅の値上がりが止まりません。
初めて新築住宅を購入する際、特に会社員の方が注意すべきポイントは以下の通りです。
将来の生活や資金計画に大きく関わるため、慎重な判断が求められます。
【資金計画とローンの注意点】新築住宅
①借りられる額と返せる額は違う
住宅ローン審査に通る金額が無理なく返済できる金額ではありません。
住宅展示場や不動産会社に紹介された専門家から「住宅ローンが通れば問題ないですよ」と言われても鵜呑みにはせず、
月々の返済額が多くとも「手取り収入の35%以内」に収まるよう計画しましょう。
②ボーナス返済に頼りすぎない
景気や転職、雇用状況でボーナスが減る可能性もあるので、基本は「毎月返済のみ」で無理のないプランを立てましょう。
ボーナスはあくまで臨時収入と考えて、貯蓄できるように家計の見直しを図りましょう。
③住宅ローン控除や減税制度を確認
制度は時期によって変更があるため、最新情報の確認を心掛けましょう。
住宅購入に関連して住宅ローン控除、すまい給付金、地域独自の補助金などがありますので
利用できる制度の見落としがないようにしましょう。
④団体信用生命保険(団信)の内容確認
万が一の際、住宅ローンの残債がゼロになる制度です。
最近では死亡時以外にもがん・三大疾病になった際にローンの残債が免除される特約を選択できることがありますので
金利と合わせて保障内容の比較をするとよいでしょう。
【住宅選びの注意点】新築住宅
⑤通勤・生活利便性を最優先に
立地の良し悪しは生活の質と資産価値に直結します。
駅からの距離や近隣にスーパーがあるか、病院や保育園などの有無も確認しておくことで
将来の生活にも影響がでてきます。
また、立地が良ければ高く売却することができるので、住宅を買い替える際に有利です。
⑥建築会社・施工会社の信頼性
実績や口コミ、アフターサポート体制をチェックしましょう。
施工ミスや引き渡し後のトラブル回避のためにも確認は必須です。
良い会社の判断が難しい場合にはご相談ください。
⑦将来の家族構成も見据えた間取り
子どもが増える、親と同居する可能性も考慮しておきましょう。
可能性がある場合には可変性のある間取りや増改築しやすい構造がオススメです。
大は小を兼ねますので、余裕があれば一部屋プラスの間取りを購入しておけばさまざまな状況に対応できます。
もし、部屋が余っている場合には書斎や趣味部屋などとしても活用できます。
【リスクへの備え】新築住宅
⑧住宅が資産ではなく「負債」になる可能性もある
新築でも価値は徐々に下がります。特に郊外のエリアは要注意です。
転勤や売却リスクも考慮して流動性を意識しましょう。
郊外であっても駐車場があり、近くにショッピングモールなど商業施設があれば
賃貸に出したり、売却も比較的に容易となります。
⑨固定資産税や維持費を忘れずに計算
購入後に毎年かかる費用があります。
固定資産税や火災保険などがあります。
またマンションでは修繕積立金や管理費があります。
年数の経過により、修繕積立金は増額されますので
購入前に長期修繕計画は必ずチェックしておきましょう。
⑩転勤・転職リスクを考慮
勤め先の将来性や自身のキャリア設計も含め、
将来、住宅を売却することも考慮して住宅を購入しましょう。
【購入までの流れ】新築住宅
- 家計の現状を把握(年収・支出・貯蓄)
- ローン借入可能額のシミュレーション
- 希望エリア・間取りなど条件の整理
- 複数の住宅展示場・モデルルーム見学
- 複数の施工会社・販売会社を比較
- 契約前に第三者の専門家(FP・宅建士など)にも相談
共働き夫婦が新築住宅を購入する際には、「収入は2人分でも、ライフイベントで変動するリスク」や「家事・育児の負担分散」が大きなポイントになります。
以下のポイントにご注意ください。
【共働き夫婦向け】新築住宅購入の注意点とアドバイス
【1】住宅ローンの組み方(無理のない計画を)
ペアローン:夫婦で別々のローンを組む方法(住宅ローン控除も2人で使える)
収入合算:片方の収入を加えて、1人でローンを組む方法
ペアローン・収入合算は慎重に考えましょう。どちらも「2人で働き続ける前提」での返済計画です。
出産・育休・病気・転職などで収入が減るリスクも考慮する必要があります。
「片方の収入だけでも返済できる」金額を基準にローンを組むようにしましょう。
例えば、夫か妻どちらかが休職・離職しても対応できると安心です。
そのために収入変動を見込んだ「余裕のある返済額」を設定しましょう。
「余裕のある返済額」については専門家(FP)に相談してみましょう。
【2】ライフイベントを見越した家選び
子育て・将来の働き方も見据えて間取りを検討することが大切です。
- 在宅勤務スペースの確保(テレワークが増加傾向)
- リビングとキッチンの動線の良さ(家事時短に直結・回廊)
- 将来的に子ども部屋にできる部屋数や間取りの柔軟性
保育園・学区・病院のチェック
子育て支援の充実した自治体も選定基準に加えてもよいでしょう。
通勤と保育園の送迎が両立できる動線が理想です。
また、小・中・高校と学区も重要です。
子どもの将来のことも考えて場所を選びましょう。
【3】共働きならではの「時間コスト」も意識
時短できる設備・住宅性能に投資することも1つです。
- 食洗機、浴室乾燥、ロボット掃除機対応の間取りなどは、家事の時短に効果大です。
- 高気密・高断熱住宅は光熱費削減&健康維持にもつながります。
通勤時間の短さ=家族の時間
安くて広い郊外は生活しやすいですが、通勤時間の少ない立地も家族との時間を持ちやすくします。
家族にとって都市部と郊外のどちらが自分たちにとって合っているのか検討しましょう。
【4】新築住宅を購入するまでの行動ステップ(共働き夫婦向け)
| ステップ | 内容 |
| 1 | 家計の共有と将来設計(子どもの予定、仕事の方向性) |
| 2 | FPに相談して、収入変動リスクも踏まえた資金計画を立てる |
| 3 | 通勤・子育て・将来性を考慮してエリア選定 |
| 4 | 土日だけでなく平日の内見も検討(時間調整は柔軟に) |
| 5 | ペアローンと収入合算の違いをしっかり理解したうえでローンを選択 |
| 6 | 希望の家がなければ建築士を利用して注文住宅の検討 |
続いて、転勤の可能性がある会社員が新築住宅を購入する際には、
「ライフスタイルの変化への柔軟さ」と「資産としての流動性」を重視することがポイントです。
以下にアドバイスをまとめますので参考にしてください。
【転勤の可能性がある人向け】新築住宅購入のアドバイス
【1】「住宅を買うべきかどうか」を冷静に見極める
少なくとも5年は住める見込みがあるか?
- 住宅ローンの初期数年間は利息負担が大きく、短期間での売却は損失リスクがあります。
- 「最低でも5年は住み続ける予定か?」が1つの判断基準です。
勤務先の転勤方針・辞令の頻度を確認
- 国内か海外か、持ち家手当・社宅制度の有無などもチェックしましょう。
- 将来的に転職の選択肢があるかでも判断が変わる。
【2】エリア選びは「流動性重視」
売りやすい・貸しやすいエリアか?
- 交通アクセスが良い(駅近、人気路線)
- 商業施設・教育施設が整っている
- 将来の人口減少リスクが低い(再開発エリアなど)
「自分が住みたい場所」ではなく、「他人も住みたがる場所」かどうかが重要です。
戸建てよりも「分譲マンション」が流動性に優れている
- マンションは貸しやすく、管理面の負担も軽い。
- 駅近であれば売却も賃貸も容易です。
【3】購入後の「転勤」に備える資金計画
空き家期間中のローン支払いに備える
誰も住まなくてもローン返済・固定資産税・管理費はかかります。
そのため最低でも6~12か月分の生活防衛資金+住宅維持費用を確保する必要があります。
賃貸に出すと家賃収入が得られるのでローン返済を賄うことができます。
そのためにも繰り返しになりますが賃貸需要のあるエリア・間取りかを購入する前に確認しておきましょう。
【4】転勤時の選択肢を事前に整理しておく
| 選択肢 | メリット | デメリット |
| 1. 単身赴任 | 家を維持できる | 家族分離・生活負担増 |
| 2. 家族で引越し+持家を賃貸 | 家賃収入が得られる | 賃貸管理、修繕義務 |
| 3. 売却 | 精算ができる | 市場価格によって損益が変動 |
どのパターンでも「想定シミュレーション」をしておくと安心です。
詳しくは専門家に相談してみましょう。
チェックリスト(転勤リスクがある人の物件購入判断)
- 勤務先の転勤制度・頻度・任期を把握している
- 少なくとも5年以上は住む前提がある
- 将来的に賃貸に出しやすいエリア・物件か確認した
- 団信・火災保険・ローンの条件をチェック済み
- 転勤時のシナリオ(単身赴任 or 売却 or 賃貸)を家族で話し合った
- 賃貸に出す際の家賃相場・管理会社の費用を調査済み
以上、新築住宅を購入する前に確認しておくべきことをまとめました。
住宅は人生で一番高い買い物なので、安易に購入して後悔しないように
しっかり準備をして取り組みましょう。