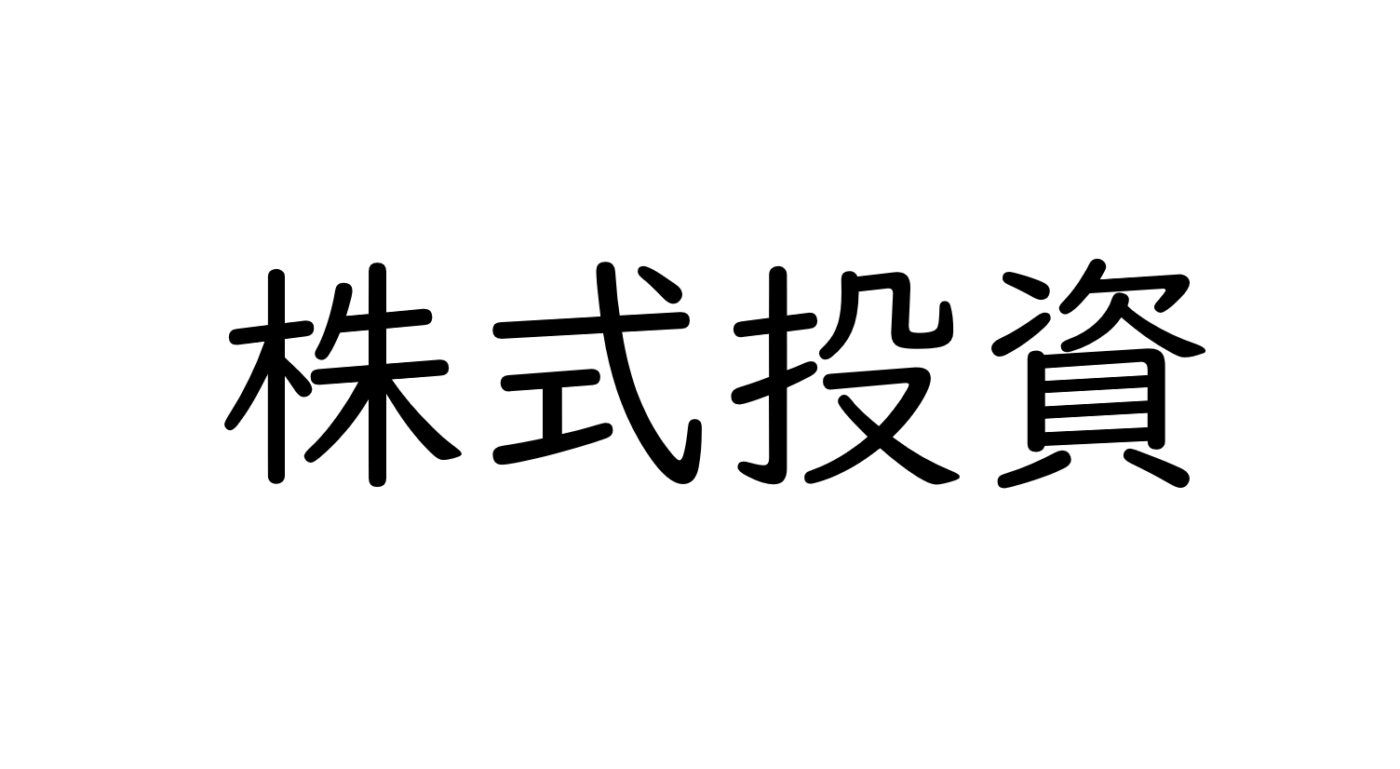株式投資を学び始めると、よく耳にするのが「信用取引」という言葉です。
通常の株式投資は自分の持っている資金を使って株を購入する「現物取引」が基本です。
信用取引は証券会社から株を借りたり、お金を借りることで手元資金以上の取引ができるのが特徴です。
初心者にとっては難しく感じますが、ポイントを押さえて仕組みやリスクを把握しましょう。
ここでは、信用取引の基本からメリット・デメリット、初心者が注意すべき点までを解説していきます。
-
信用取引の基本的な仕組み
信用取引とは、証券会社に一定の保証金(担保となるお金や株)を預け、その保証金をもとに「株式」や「お金」を借りて取引する方法です。
信用取引には大きく分けて2つの取引方法があります。
-
信用買い(買建て)
証券会社からお金を借りて株を買う方法です。手元資金の約3倍まで株を購入できるため、少ない資金で大きな投資が可能になります。株価が上がれば大きな利益を狙えますが、反対に下がれば損失も拡大します。
-
信用売り(空売り)
証券会社から株を借りて売る方法です。株価が下がると安く買い戻して利益を得られます。通常の現物取引では株価が上昇しなければ利益は出せませんが、信用売りを使えば株価の下落局面でも利益を狙えるのが特徴です。
-
現物取引との違い
現物取引と信用取引の最大の違いは「自己資金の範囲内で取引するか」「資金や株を借りて取引するか」です。
現物取引はシンプルで、購入代金を支払って株を持ち、売却すれば現金が戻ってきます。
損失は最大でも投資した金額に限定されます。
一方、信用取引ではレバレッジが効くため、少額資金でも大きな取引が可能です。
しかし損失が投資額を超える可能性もあります。
つまり「利益も損失も大きくなりやすい」という点で、現物取引とは根本的にリスク構造が異なります。
-
信用取引のメリット
信用取引には、現物取引にはない大きなメリットがあります。
- レバレッジ効果
手元資金の約3倍まで取引できるため、資金効率が高まります。例えば100万円の資金で最大300万円分の株を買えるため、株価が上がれば現物取引よりも大きな利益が期待できます。 - 空売りができる
株価が下がる局面でも利益を狙えるのは、信用取引ならではの魅力です。相場が下落基調でも柔軟に立ち回ることができます。 - 短期売買に向いている
資金効率が良いため、デイトレードや短期売買に適しています。少しの値動きでも利益を積み重ねることが可能です。
-
信用取引のリスク・デメリット
一方で、信用取引には初心者にとって非常に大きなリスクがあります。
-
損失が拡大する
レバレッジをかけている分、株価が思惑と逆に動くと損失も大きくなります。場合によっては元本以上の損失を抱えることもあり、借金を抱えてしまう可能性ががあります。
-
追証(追加保証金)のリスク
信用取引では保証金を担保にしていますが、株価が大きく下がると担保不足が発生します。その際、証券会社から「追証」を求められ、追加で資金を入れなければなりません。対応できないと強制的にポジションを解消され、大きな損失につながります。
-
期限がある
信用取引は無期限ではありません。一般的に6か月以内に決済しなければならず、長期投資には向いていません。株価が思うように動かなくても、期限が来れば強制的に決済されます。
-
金利や貸株料がかかる
お金や株を借りて取引しているため、一定の金利や貸株料がかかります。長期間持ち続けるとコスト負担が増え、利益を圧迫します。
-
初心者が信用取引で注意すべきポイント
信用取引は強力な武器にもなりますが、初心者が安易に手を出すと大きな失敗につながりやすい投資手法です。注意点を整理すると次の通りです。
-
最初は小さな金額から始める
いきなり最大限のレバレッジを使うのは危険です。まずはリスクを抑えて練習することが大切です。
-
損切りルールを徹底する
株価が思惑と逆に動いたら、早めに損切りするルールを設けましょう。ずるずると持ち続けると損失が膨らみます。
-
追証を避けるよう管理する
保証金維持率を常にチェックし、余裕をもった資金管理を心がけましょう。無理のないポジションを取ることが重要です。
-
長期保有は避ける
信用取引はあくまで短期向きです。長期投資は現物取引に任せる方が安全です。
信用取引は「諸刃の剣」
信用取引は、資金効率を高め、株価の上昇だけでなく下落局面でも利益を狙える便利な手法です。
しかし、その裏側には「損失が拡大する」「追証が発生する」「期限がある」といった大きなリスクも存在します。
初心者にとってはリスクが大きいため、いきなり本格的に利用するのは避けるべきです。
まずは現物取引で基礎を固め、資金管理や損切りの大切さを身につけてから挑戦しましょう。
信用取引は、使いこなせば投資の幅を大きく広げる武器になります。
しかし、同時に大きな損失を生む可能性がある「諸刃の剣」であることを忘れてはいけません。
リスクを正しく理解し、慎重に活用することが成功への第一歩となるでしょう。
信用取引に向いている銘柄の特徴
-
出来高が多い(流動性が高い)銘柄
信用取引は短期で売買するケースが多いため、スムーズに売買できる銘柄が望ましいです。
出来高が少ない銘柄は売りたいときに売れなかったり、想定外に株価が動いたりするリスクがあります。
東証プライムに上場している大企業や人気テーマ株は流動性が高く、信用取引に適しています。
-
値動きが活発な銘柄
信用取引では株価が大きく動くほど利益を得やすくなります。
逆に値動きが小さい銘柄ではレバレッジをかけても効率が悪いです。
短期的にトレンドが出やすい「成長企業」「材料が出て注目されている銘柄」は信用取引に向いています。
値動きが激しすぎる銘柄(仕手株や新興市場の一部)は大きな利益も狙えますが、リスクも高いです。
信用取引では損失拡大の危険があるため、極端に乱高下しない銘柄を選ぶのが理想です。
たとえば、日経平均やTOPIXに連動するETFも人気です。
-
貸借銘柄(空売りが可能な銘柄)
信用取引の魅力のひとつが「空売り」です。
ですが、すべての銘柄で空売りができるわけではありません。
証券取引所が指定する「貸借銘柄」だけが空売り可能です。
相場が下がる局面でもチャンスを狙うなら、貸借銘柄を選ぶ必要があります。
-
情報が豊富で分析しやすい銘柄
信用取引は短期の判断が求められるため、情報収集しやすい銘柄の方が有利です。
大企業や市場で話題になっている株はニュース・アナリストレポート・SNSなど情報源が多く、相場の流れをつかみやすいです。
逆に情報が少ない中小型株は予想が難しく、初心者には向きません。
-
出来高と株価水準のバランスが良い銘柄
信用取引では「板(売買注文の状況)」が厚い方が安定して取引できます。
また、株価があまりにも高い銘柄は少額でも大きな資金を必要とし、リスクが大きくなります。
初心者の場合は、1,000円~5,000円程度の株価で流動性がある銘柄を選ぶと扱いやすいです。
初心者が最初に取り組むなら、日経平均株価に連動するETFや、流動性の高い大型株から始めるのがおすすめです。
信用取引に向いている人の特徴
-
リスク管理が徹底できる人
信用取引はレバレッジが効く分、少しの値動きで大きな損益が出ます。したがって
「損切りラインを決めたら必ず実行できる」
「資金を分散して無理な建玉をしない」
といった自己管理ができる人が向いています。
逆に感情で取引してしまう人には不向きです。
-
短期売買に慣れている人
信用取引は6か月以内に決済が必要なため、長期投資には不向きです。
デイトレやスイングなど短期売買の経験があり、相場の値動きに素早く対応できる人が適しています。
現物取引で短期売買の練習を積んでから信用取引に挑むのが理想です。
-
相場や銘柄の分析ができる人
テクニカル分析やファンダメンタルズ分析をある程度できる人は信用取引を活かしやすいです。
情報を集め、トレンドや相場の流れを読み取る力があれば信用取引をプラスに働かせることができます。
逆に「なんとなく上がりそう」と感覚で取引する人は大きな損失を抱えやすいです。
-
余裕資金で投資している人
信用取引は損失が大きくなりやすく、追証(追加保証金)のリスクもあります。
生活資金や借金に頼る人は絶対に避けるべきです。
資産の一部、余裕資金でリスクを取れる人こそ信用取引に適しています。
-
冷静さを保てる人
株価は日々上下します。
そのたびに一喜一憂して感情的になる人は、信用取引では失敗しやすいです。
たとえ含み損を抱えても冷静に判断し、事前に立てたルール通りに行動できる人は信用取引を扱う素質があります。
-
学び続ける姿勢がある人
信用取引はルールや制度(委託保証金率、建玉制限、逆日歩など)が複雑で、知らないと損をすることもあります。
常に勉強し、制度変更や市場環境に対応できる人が成功しやすいです。
「知識武装してから挑戦する」という姿勢が欠かせません。
つまり信用取引は「投資経験を積み、自己管理ができる人」に適しており、「初心者が一発逆転を狙う道具」ではありません。
現物取引で経験を重ね、資金管理や感情コントロールができるようになってから少しずつ活用するのが安全です。
建玉制限とは?
「建玉(たてぎょく)」とは、信用取引で現在保有している未決済のポジション(買い建てや売り建て)のことを指します。
建玉制限とは、投資家が信用取引で保有できる建玉の数量や金額に制限を設ける仕組みのことです。
簡単に言うと、「信用取引で無制限に株を買ったり売ったりできないように、証券会社や取引所が上限を決めている」というルールです。
なぜ建玉制限があるのか?
信用取引は証券会社から「お金」や「株」を借りて行う取引です。
無制限に取引できると、株価が急変したときに証券会社や市場全体に大きなリスクが及びます。
そのため、投資家の建玉に上限を設けて、過度な取引や市場への悪影響を防いでいるのです。
建玉制限の具体例
-
委託保証金率による制限
信用取引を行うには、まず「委託保証金」と呼ばれる担保を証券会社に預けます。
建玉を増やせる量は、この保証金の金額と「保証金率」で決まります。
例:委託保証金:100万円 保証金率:30%
この場合、約333万円(100万円 ÷ 30%)まで建玉を持てる、という制限がかかります。
-
銘柄ごとの建玉制限
特定の銘柄について、証券取引所や証券会社が「建玉数量の上限」を定めることがあります。
これは、株価操作や過度な投機を防ぐ目的があります。
例:東証が指定した銘柄では「一人あたり建玉上限 5万株まで」と決められることがある。
制限を超えると、新たな建玉はできなくなります。
-
証券会社独自の制限
証券会社によっては、リスク管理のため独自に建玉制限を設けている場合もあります。
特にボラティリティ(値動きの激しい)銘柄では「建玉上限を少なく設定」するケースがあります。
投資家にとっての注意点
建玉制限に引っかかると、新しい信用取引の注文ができません。
すでに建玉を持っている場合は、決済して建玉を減らす必要があります。
保証金率が下がると(株価が下がったりして担保不足になると)、自然と建玉可能額も減り、追証(追加保証金)が発生することもあります。
建玉制限とは、信用取引で持てるポジション(建玉)の上限を決める仕組み
保証金率・銘柄ごとの規制・証券会社独自のルールで制限される
投資家の過度な取引を防ぎ、市場の安定性を保つために存在する
信用取引を行う際には、必ず「自分がどれだけの建玉を持てるのか」を証券会社の画面で確認し、余裕を持った取引をすることが重要です。
逆日歩とは?
逆日歩とは、信用取引で株を空売りしたときに発生する「追加のコスト(貸株料)」 のことです。
信用売りは、証券会社を通じて「市場から株を借りて売る」仕組みになっています。
その株を借りる需要が高まり、株の調達が難しくなると、通常の貸株料に加えて「逆日歩」という特別なコストが発生します。
投資家が証券金融会社や他の投資家に支払う“株を借りるための追加料”と考えるとイメージしやすいです。
逆日歩が発生する仕組み
- 投資家が空売り注文を出すと、証券会社は株を用意する必要があります。
- 需要が多く供給が足りないと、株を調達するためにコストが上がります。
- そのコストを空売りしている投資家が負担する形で「逆日歩」として請求されます。
要するに、「空売りが集中して、株不足になったときにかかる追加料」です。
逆日歩が発生しやすいケース
株主優待銘柄
優待の権利確定日前は、優待を受けたい投資家が現物買いを増やします。
一方で優待タダ取りを狙う「クロス取引(買いと売りの両建て)」が増えるため、空売り需要が急増し、逆日歩が発生しやすくなります。
人気の小型株
発行株数が少ない銘柄は市場に出回る株が限られているため、空売りが集中するとすぐに株不足になりやすいです。
市場で急に注目を集める銘柄
ニュースやテーマ株で急騰した銘柄は「空売りで下落を狙おう」という投資家が増え、逆日歩が発生することがあります。
逆日歩の金額
逆日歩の金額は毎日変動します。
証券金融会社が「品貸料率(逆日歩の基準)」を公表し、それに基づいて計算されます。
数円で済むこともあれば、人気の優待銘柄などでは数百円〜数千円になることもあります。
例:
株価2,000円の銘柄を100株空売り → 逆日歩が1株あたり50円発生した場合
50円 × 100株 = 5,000円 の追加コスト
1日単位で発生するため、保有日数が長いほど負担が増えます。
投資家にとっての注意点
予測できない
逆日歩がどれくらい発生するかは事前に完全には読めません。
空売りをする際は「逆日歩が出るかもしれない」と想定する必要があります。
長期保有は危険
空売りした銘柄を長く持ち続けると、逆日歩でコストが膨らみ、含み益が吹き飛ぶこともあります。
優待銘柄の空売りは要注意
とくに株主優待の権利確定日直前は、逆日歩が高額になりやすいです。
逆日歩のまとめ
逆日歩=空売りの追加コスト(貸株料)
株不足になると発生し、金額は日々変動する
優待銘柄や人気株、小型株などで発生しやすい
長期保有や無計画な空売りは危険
信用取引で空売りをする際は、逆日歩がかかるリスクを念頭に置き、短期での利用や銘柄選びの工夫が大切になります。
追証(おいしょう)とは?
信用取引では「委託保証金」という担保を証券会社に預けて取引します。
株価が大きく下がる(または上がる)と、保証金が不足してしまうことがあります。
その不足分を補うために証券会社から請求されるのが 追証(追加保証金) です。
追証を払わないとどうなる?
-
支払期限がある
通常、追証が発生すると翌営業日までに不足額を入金しなければなりません。
証券会社によっては当日中に入金を求められることもあります。
-
払わない場合は強制決済(ロスカット)
期限までに追証を入金しないと、証券会社は投資家の持っている信用建玉(買い・売りのポジション)を 強制的に反対売買して清算 します。
これを「強制決済」または「ロスカット」といいます。 -
損失が確定する
強制決済でポジションが閉じられると、損失が確定します。
本来なら株価が戻る可能性があったとしても、待つことができずに損切りされてしまうわけです。
-
損失が保証金を超えた場合は借金になる
さらに怖いのはここです。強制決済をしても損失が保証金でカバーできなければ、その差額を投資家が証券会社に 現金で返済(借金) しなければなりません。
たとえばリーマンショックやコロナショックのような急変時には、一夜にして大きな追証が発生し、返済不能に陥るケースもあります。
追証を払わないとどうなるか?
・強制的にポジションを清算される
・損失が確定する
・損失が保証金を上回れば借金を背負う
つまり「入金しない=損失確定+最悪の場合は借金」という、とても厳しい結果になります。
投資初心者へのアドバイス
追証が発生しないようにするには、下記に留意しましょう。
・レバレッジをかけすぎない(建玉は余裕資金の範囲内)
・損切りルールを徹底する
・値動きの激しい銘柄を避ける
※株式投資はリスクの高い投資です。投資は自己責任で無理なく行いましょう。投資で被った損失について弊社は一切の責任を負いません。