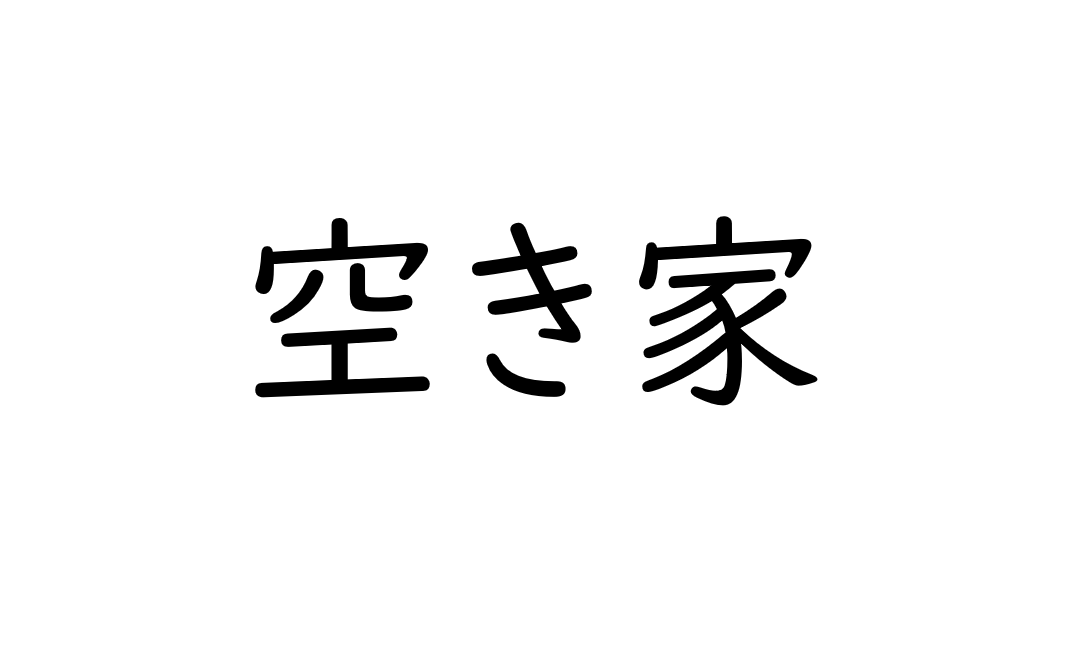昨今、空き家問題が話題になっています。
不動産を相続した人が早く空き家を処分した方が良い理由は複数あります。
特に放置することで生じる経済的・法的・社会的リスクが大きいため、早期の判断・対応が重要です。
このコラムでは空き家を放置するリスクと、その対策について具体的に解説していきます。
空き家を所有していると固定資産税・維持費がかかり続ける
空き家でも固定資産税や都市計画税は毎年発生します。
管理を怠ると草刈り・清掃・害虫駆除・修繕などの維持費もかさみます。
そのため、利用していないのにお金だけが出ていく「負動産(ふどうさん)」になりかねません。
空き家は「特定空家」に認定されると税負担が増える
管理が不十分な空き家は、自治体から「特定空家」に指定される場合があります。
そうなると、固定資産税の軽減措置(最大1/6)が解除され、税額が6倍になることも。
行政からの指導により費用が発生するリスクもあります。
老朽化による事故・責任リスク
倒壊や屋根の落下により通行人がケガをしたり、隣地への越境などが発生したりすれば、所有者が損害賠償責任を問われます。
放火や不審者の侵入といった犯罪の温床にもなりやすく、地域の安全にも悪影響があります。
市場価値が下がる可能性
時間が経つほど建物は劣化し、資産価値が下落します。
特に地方の空き家や築古物件は、早めに手放さないと買い手がつきにくくなる傾向があります。
相続人同士のトラブル回避
空き家を共有で相続していると、売却・活用について意見が割れることがあります。
時間が経つと相続人の高齢化や死去により、権利関係が複雑化(数次相続)し、処分が困難になります。
放置は危険。早期判断が資産を守る
空き家は「持っているだけでコストとリスクが増える」存在になりやすいため、
活用しない空き家は早めに「売却」することが、経済的にも精神的にもよいでしょう。
空き家を処分するには、まず現状把握→方針決定→実行のステップを踏むことが大切です。
以下にわかりやすく「空き家処分の進め方」をまとめます。
空き家処分の進め方【7ステップ】
① 相続登記・名義変更を済ませる(法的な整理)
不動産を正式に相続した後は、名義変更(相続登記)を行います。
2024年4月からは相続登記が義務化され、3年以内にしないと過料(10万円以下)の対象になるので注意が必要です。
必要な書類として遺言書・戸籍謄本・相続関係図・固定資産税評価証明書などがあります。
② 現地調査(建物・土地の現況を把握)
空き家の劣化状況・構造・築年数・接道・用途地域などをチェックします。接道の有無や用途地域により売却の難易度が大きく変わります。
必要であればホームインスペクション(住宅診断)を依頼(3〜10万円程度)することもありますが、築年数が古い場合には実施しなくてもよいでしょう。
写真を撮って記録しておくと、不動産業者とのやり取りがスムーズになります。
③ 近隣・権利関係の確認
境界トラブルや越境がないかを確認。あれば測量士による境界確定測量も検討します。
共有名義の場合は、他の相続人の同意も必要となります。
④ 処分方針を決める(売却/解体など)
選択肢ごとの概要は以下の通りです。
| 方法 | 特徴 |
| 売却(建物付き) | 建物に価値があれば有利。すぐ現金化したい人向け。 |
| 売却(更地) | 建物に価値がないなら解体して更地にして売る。
ただし、市街化調整区域や再建築が付加な場合は解体せずに 古家付き土地として売却した方が有利な場合も |
| 解体して保有 | 固定資産税は増えるが、リスクを軽減できる。将来売却や活用の準備に。 |
※地域や建物状況に応じて、専門家と相談しながら実施することをオススメします。
⑤ 不動産会社・専門家に相談
空き家の取引に慣れている不動産会社に査定依頼。
複数社に相談して「仲介か買取か」も検討(早く現金化したいなら買取も有力)。
必要に応じて、司法書士・税理士・土地家屋調査士とも連携する。
⑥ 補助金・税優遇を活用
自治体によっては「解体費用補助」などの支援制度があります。
早めに自治体の制度を確認しておきましょう。
また、譲渡から3年を経過する年の12月末までに空き家を売却すれば譲渡所得から最高3000万円の控除が受けられます。
⑦ 実行(売却契約・解体)
方針が決まったら、実行フェーズへ。
売却の場合は買主との契約、解体なら業者選定との契約などを行います。
税金(譲渡所得税など)にも注意し、確定申告の準備もしておきましょう。
空き家処分でよくある失敗
・建物に価値があると思っていたが、実はマイナス評価だった
・解体したら売れると思ったのに、費用倒れになった
・相続人同士の意見が合わず放置されてしまった
・近所から苦情が来て慌てて処分に動いた
これらを防ぐには、「早めに専門家に相談して動く」ことが一番大切です。
弊社でも不動産についての相談を受け付けていますので、気軽にご相談ください。