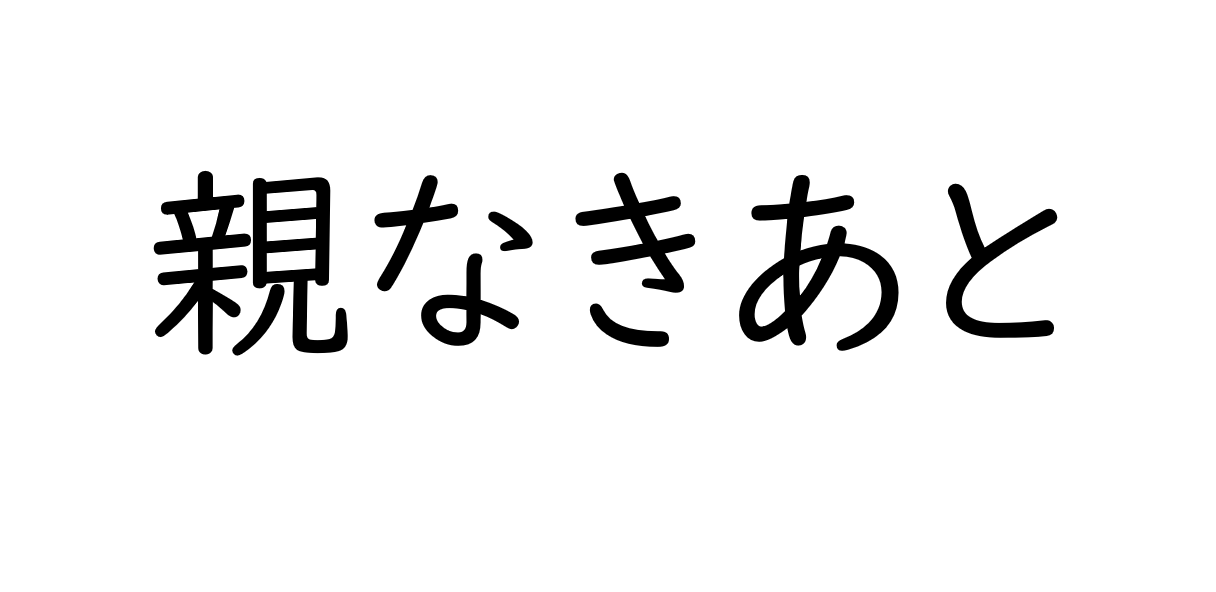障がいを持つ子やひきこもりの子がいる親御さんは将来のことを色々と心配されているのではないでしょうか。
可愛いわが子のために何ができるのか?親なきあとのことを考えるにあたって参考になればと思い情報提供をさせていただきます。
何から準備をすれば良いのか?
まずは『ライフプラン(人生設計)』が必要です。
その理由は「将来について見通しておいた方がよい」からです。
そして、一度、ライフプランを作成したら終わりではなく、「定期的な見直し」は必要です。
漠然とした不安を明確な数字に落とし込むことで、具体的に必要となる金額がわかるので資金のめどが立ち、不安を安心に変えることができます。
またライフプランは「親」と「子」それぞれ必要です。
子どものために将来のライフプランとして親がすべき3つのこと
1 資産の整理
2 子どもの住居
3 お金の管理
1 資産の整理
親が平均寿命まで生きた場合、資産をどれくらい子どもに残せるか計算する
・1年間の収支を計算する
・自分たちが持っている金融資産の棚卸しをする
・不動産の売却価格を調べる⇒漠然とした不安を「見える化」できる
親の資産だけで足りないとわかれば
「月○○万円の収入がないと
○○歳のとき資産が底をつく」と具体的に経済状況を子どもに説明することができます。
具体的に必要な金額がわかれば、子どもが今後、仕事を探しやすくなります。
もし、お子さんが働くことが難しい場合、いかにお金を準備するのか考える必要がでてきます。
2 子どもの住居
住居の確保は子どもにとって重要です。
『持ち家なら安心か?』と言われると、それだけでは不十分です。
築古の場合、子どもが一生住めるでしょうか?おそらく修繕が必要となります。
その場合、お子さんが自ら業者に修理を頼めるでしょうか?
両親が事前に親子経営や若い担当者がいる工務店を見つけて、軽微な家の修理を頼むことで、家の状況を知ってもらうことができます。
そして将来、子どもがひとりになっても修理を頼める体制を作るなど対策をしておくと良いでしょう。
賃貸であれば、手頃な中古住宅を両親が購入することで、親なきあとでも家賃を払う負担は無くなります。
住宅ローンは借金ですが、最終的には子どもに「自宅」という財産を遺すことができます。
3 お金の管理について
可愛い子供が悪い大人にだまされるのではないかと心配になるのは当然です。
最近では詐欺のニュースも頻繁に流れています。
大切な財産を守るには?金銭管理はどうしたら良いのでしょうか?
成年後見人制度
例えば「成年後見人制度」を利用するという選択肢があります。
後見人制度では弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門家が後見人となり、被後見人の財産を守ります。
また各事業者や介護サービスなどの契約も本人に代わって行ってくれます。
他にも、株式や投資信託などの有価証券や収益不動産などが
障がいのある子の名義となった場合、管理は後見人の判断となります。
その場合、家族が自由に売買などできなくなります。
家族で資産を管理したい場合には、名義を親や兄弟姉妹にしておく方がよいでしょう。
また「家族信託」という選択肢もあります。
家族信託
家族信託では特定の預貯金・有価証券・不動産などを家族が自由に管理することができます。
そのため、資産の名義人が認知症になったり、亡くなったりしても家族が継続して管理することができます。
任意後見制度
その他にも、本人が元気なうちに大切なことを信頼できる人や団体にお願いする任意後見制度があります。障がいのある子が18歳未満であれば両親には親権があるので、子のために任意後見の手続きをすることができます。
任意後見を誰にお願いするかというと、子のことを一番わかっている両親自身にすれば子にとっても両親にとっても良いのではないでしょうか?
専門家は信頼できるかもしれませんが、あくまで他人です。
ただ、親族が成年後見人に選ばれる要件として次の4点に注意が必要です。
- 本人の財産が少ない
- 収益物件がない
- 高齢でないこと
- 遠方でないこと
生命保険の活用
生命保険は受取人を指定できます。また相続税非課税枠として相続人1人につき500万円。
死亡後、すぐに口座へ振り込まれ、遺留分の算定対象外などのメリットがあります。
資産の内訳で不動産が多い場合は生命保険で現金を準備しておくことをお勧めします。
また手元にまとまった現金があると使い切ってしまうリスクがある場合、生命保険に形を変えて月々分割して受け取ることも可能です。その場合は収入保障保険などを活用すると良いでしょう。この保険は、毎月一定の金額を生活費のように保険会社から振り込んでもらえます。
生命保険で老後資金を準備する場合には「変額個人年金保険」が便利です。インフレに対応でき、途中で一部を解約することができます。さらに、満期になって受け取る際には年金形式で分割して受け取ることもできます。
死後事務委任契約
成年後見制度では死後の葬儀や納骨には対応していません。そのため、死後事務委任契約を締結しておくと安心です。必要な手続きは次の2点です。
①葬儀社と受任者を見つける
②内容を決め、公証役場で手続きをする(公正証書)
できれば地域とのつながりを積極的にもち、わかりやすいところ(冷蔵庫など)に緊急連絡先を張っておくと
いざという時に慌てなくて済みます。
死後事務の主な内容は次の通りです。
・訃報連絡 ・遺体の搬送 ・役所へ死亡届の提出 ・葬儀の立ち合い
・賃貸や公共サービスの解約 ・遺品整理 ・カード類の解約
・ペットの引継ぎ など
障がい者扶養共済(しょうがい共済)
大切な子へお金を遺す方法として障がい者扶養共済があります。
1口2万円もらえる終身年金で2口まで加入が可能です。
毎月、少額(2万円or4万円)が渡されます。
申込は市役所などでできます。掛金が全額控除され、付加保険料が不要な優れた共済です。
加入要件は65歳未満で健康であることで、契約者・被保険者は両親になります。
加入者が亡くなる、もしくは重度障害になると支給が開始されます。障害年金や生保には影響せず(収入ではない)、相続税・贈与税の対象外というのもメリットですね。
将来のことを考えると不安なことはありますが、できる対策は早めに準備をして少しでも不安を安心にかえていきましょう。