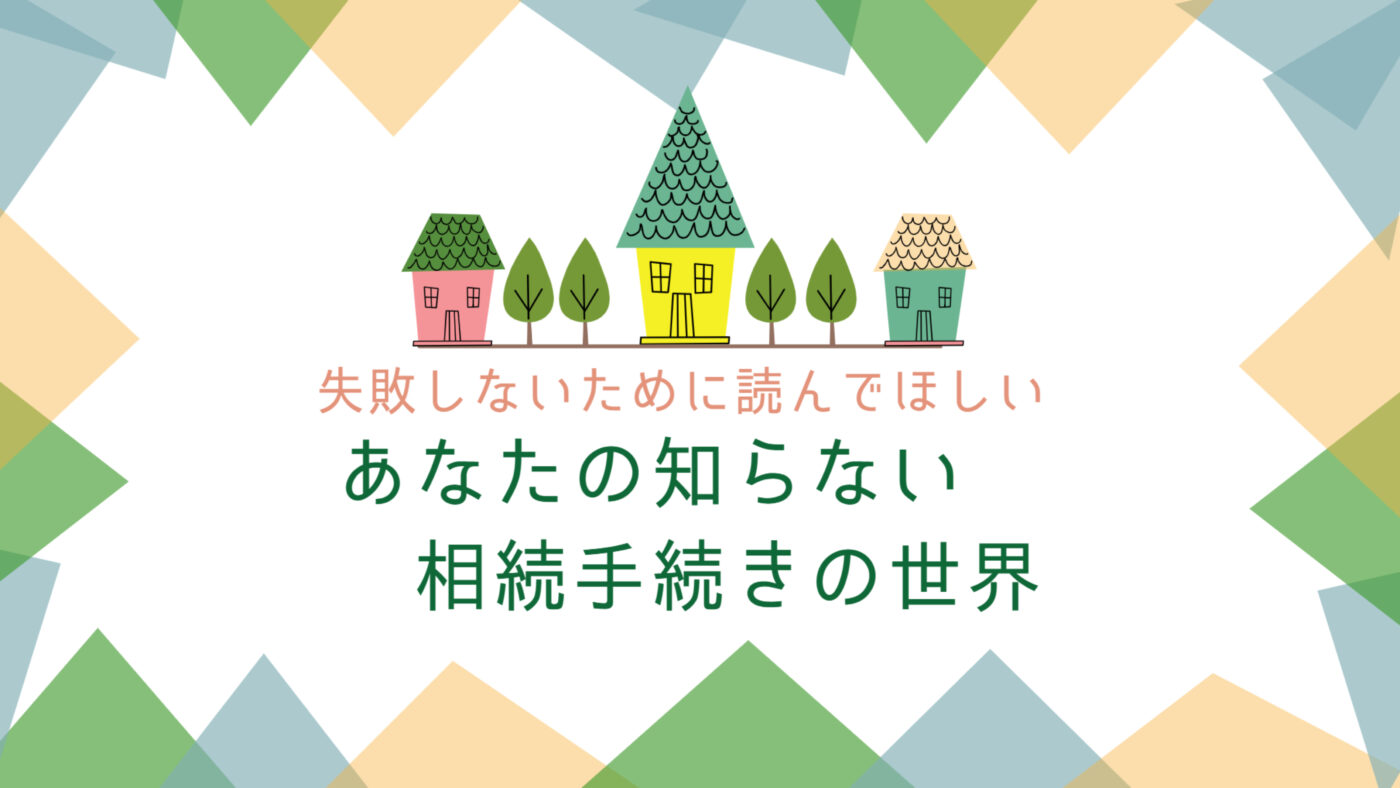みなさん、こんにちは。
相続手続きカウンセラーの山原です。
本日は「相続手続きの前に遺言書を探しましょう②」をおつたえします。
あらゆる相続手続きに最も影響を与えるのは「遺言書があるかどうか」です。
前回のコラムで「遺言書の種類」についてお伝えしましたが、生前に遺言書の有無や保管場所を聞いていないと探し出すのは至難の業かもしれません。
■遺言書の探し方
●公正証書遺言の検索
1989年1月1日以降の公正証書遺言は日本公証人連合会でデータベース化されているので、亡くなった人の公正証書遺言はこの検索システムを利用することで作成の有無を確認できます。
検索料金は無料で、全国どこの公証役場でも検索できます。
もし遺言書が保管されていた場合には、保管されている公証役場に請求をして遺言書の謄本を発行してもらえるため、この遺言書を利用して相続手続きをすすめることができます。
データベースには以下の情報が登録されています。
- 公正証書遺言の作成日
- 証書番号
- 遺言書を作成した公証役場
- 公証役場の所在地
- 電話番号
- 公証人の氏名
遺言検索システムを利用することにより、上記のような公正証書遺言の情報は確認できますが「遺言の内容」までは確認することはできません。
内容を確認するには、公正証書遺言を保管している公証役場で手続きをする必要があります。
また、遺言者が生存している限り、遺言検索が利用できるのは遺言者のみです。
遺言者が遺言検索を利用する場合は、遺言者の本人確認資料が必要です。
たとえ家族であっても
(遺言書を書いているか知りたい・・・)などの理由で検索することはできませんので
ご健在の間は直接ご本人に確認してみましょう。
●自筆証書遺言の探し方
まず自宅や病院、入所していた施設などを探してみましょう。
すぐに見つからないときは、以下の場所を重点的にチェックしてみてください。
- 金庫
- 書斎の机や鍵の付いた引出し
- 通帳や保険証券といった財産に係る資料の保管場所
- 車の中
- 日記やアルバムの中
- 仏壇の中や仏壇の周辺
- 冷蔵庫
- 本棚
- 銀行の貸金庫(※通帳の取引履歴で貸金庫の利用料金が引き落とされているかを確認)
「遺言書を書いていたことは確かだけど、どこを探しても見つからない」
という場合は『遺言書保管事実証明書』の交付請求を行ってみるとよいでしょう。
2020年7月に、自筆証書遺言を対象とした遺言書保管制度が始まっており、この制度を利用している場合には亡くなった方が法務局に自筆証書遺言を預けているかどうか確認できます。
知人の中には「一番信頼できる長年のご友人に預けている」という方もいらっしゃいました。
懇意にされている趣味のお仲間がいる方などは、それとなく尋ねてみると遺言書の保管について糸口がみつかるかもしれません。
■自筆証書遺言を見つけたら
見つけたらすぐに遺言執行ができる公正証書遺言と異なり、自筆により書かれた遺言書は手順があります。
まず、見つけた遺言書を決して開封してはいけません。発見した人はすみやかに家庭裁判所で「検認申立」をする必要があります。
「検認」とは相続人に対して遺言の存在と内容を知らせるとともに、遺言書の偽造・変造を防ぐために、遺言書の状態等を裁判所で確認する手続きです。この「検認手続き」を行わないと相続手続きをすすめることができません。
また、検認をしないで遺言を執行したり、裁判所以外で開封すると「5万円以下の過料に処する」と定められています。
「検認手続き」は裁判所の繁忙状況などにより申立から検認をおえるまで数ヵ月かかることがあります。
私の知っている事例でも4ヵ月かかったのですが、この期間は遺言の内容を知ることもできず相続手続きが保留状態となるので、遺言書によって相続手続きがスムーズにすすめられると思っていたご家族とすれば、イライラが募る時間となってしまいました。
例えば、相続税の納付は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告しなければなりませんが、遺言書の内容を確認するだけで4ヵ月かかっていては、あっという間に期限が来てしまうので注意が必要です。
■自筆証書遺言を「検認なし」で相続手続きに使える方法
この「検認」をせずに自筆証書遺言を相続手続きに使える方法があります。
それは、法務局の内部にある「遺言書保管所」で自筆証書遺言書を保管してもらえる「自筆証書遺言書保管制度」を利用することです。
この制度は自筆証書遺言の様々な問題点を改善するために2020年7月10日より運用が開始されました。
2021年の月間利用件数は約1400件(法務局/民事局発表)となっています。
【メリット】
- 遺言執行の際の検認が不要
- 遺言書の紛失・廃棄・隠匿・改ざんを防げる
- 遺言の形式要件を満たしているかどうかチェックしてくれる
- 遺言書が保管されている旨が相続人に通知される
【デメリット】
- 遺言書の内容はチェックしてくれない
- 保管の申請は本人が法務局で行う必要がある

その他のメリットとして「自筆証書遺言書保管制度」では遺言書を画像データ化してくれるという点があげられます。
これは、東日本大震災の際に宮城県などの法務局に保管されていた多くの遺言書が滅失してしまったことを教訓に、万が一の事態も考慮して原本を電磁的記録化して、これをその原本とは別に保管する「原本の二重保存」を実施するようになったそうです。
相続人等は遺言書原本が保管されている遺言書保管所にかかわらず、全国どこの法務局においてもデータによる遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付が受けられます。
このように、遺言書の種類や保管方法によって異なるルートで相続手続きがスタートします。
では、遺言書がなかった場合、相続手続きはどうなるのでしょうか?
次回のコラムでお伝えします。
(2022年11月20日時点の情報に基づいています)