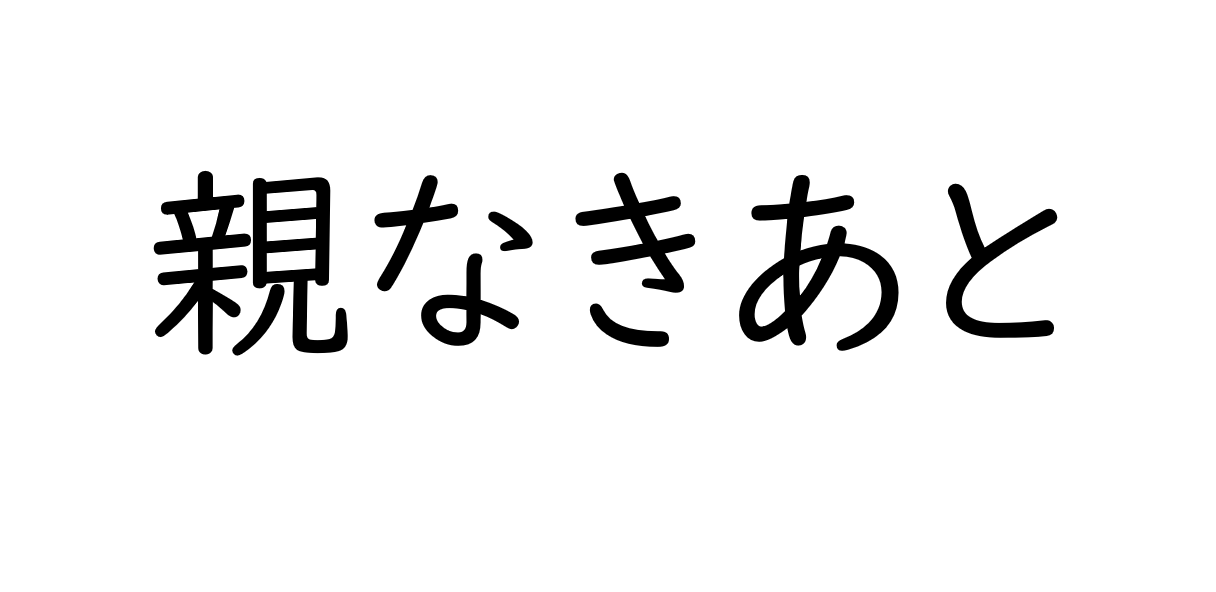【はじめに】親が抱える「将来への不安」
障害のある子どもを育てる親が共通して抱える大きなの不安の1つは「自分がいなくなった後、この子はどう生きていくのか」という点です。
元気なうちは面倒を見られても、親の高齢化・病気・死去といったライフイベントは避けられません。
そのときにわが子の「生活費は?」「住まいは?」「支援してくれる人は?」という課題が一気に表面化します。
この「親亡き後の問題」を回避するために、早いうちからお金と制度の仕組みを整えておくことが極めて重要です。
このコラムでは、障害のある子を持つ家族が準備すべき「経済的な仕組み」と「制度の活用方法」をわかりやすく解説します。
まずは把握すべき「生活にかかるお金」
障害のある子の生活費は一般的な家庭よりも多くなる傾向があります。
医療・介護・交通・教育など、見落とされがちな出費が積み重なるためです。
たとえば、
・医療費・通院費(月1〜2万円)
・通所施設、作業所への交通費
・特別支援学校や福祉施設の利用料
・将来のグループホーム入居費(家賃+食費など)
こうした費用は「障害基礎年金」や「特別児童扶養手当」などである程度カバーできますが、十分とは言えません。
そのため親の資産設計や保険・信託の仕組みづくりが将来の安定に直結します。
「親亡き後」に備える3つの仕組み
親がいなくなった後も子どもが安心して生活できるようにするためには、「お金の管理」と「法的な後ろ盾」をセットで準備する必要があります。
①成年後見制度
判断能力が十分でない場合、成年後見人が財産管理や契約を代行します。
親が元気なうちに「任意後見契約」を公正証書で結んでおくことで将来スムーズに支援体制を移行できます。
ただし、後見人には毎年の報酬が発生するため他の仕組みと組み合わせてコストを抑える工夫が必要です。
②遺言書の作成
親が亡くなった後の財産分けでトラブルが起こらないよう遺言書の作成は必須です。
特に障害のある子に多めに遺す場合は他の兄弟の理解を得る工夫も必要となります。
「公正証書遺言」を作成して専門家に相談しながら文面を整えると確実です。
③福祉型信託(民事信託・特定贈与信託)
最近注目されているのが「親亡き後のための信託制度」です。
たとえば特定贈与信託では、親が生命保険金や預金を信託銀行に託して障害のある子どもが亡くなるまで定期的に支給される仕組みが作れます。
税制上も優遇があり、相続税の対象外になる場合もあります。
家族で共有すべき「生活設計」と「情報」
制度やお金の仕組みを整えるだけでは十分ではありません。
実際に支援が必要になった時にスムーズに動けるよう「家族間の情報共有と体制づくり」も欠かせません。
①家族会議を開く
親が元気なうちに兄弟姉妹や親族と「将来の役割分担」について話し合いましょう。
後見人・遺言執行者・信託受託者などを誰が担うかを明確にしておくことがトラブル防止になります。
②情報ノートの作成
「支援ノート」や「ライフノート」に子どもの医療・福祉・生活の情報をまとめておきます。
たとえば以下のような内容を残しておくと安心です。
・医療機関・服薬情報
・福祉サービス・担当支援員の連絡先
・好きな食べ物・生活リズム・支援上の注意点
・金融機関・保険・信託の一覧
これらを定期的に更新して信頼できる家族や支援者と共有しておくことが大切です。
「お金を遺す」より「仕組みを残す」という発想へ
親の立場から見ると「どれだけ財産を残せるか」に目が行きがちです。
しかし、本当に大切なのは「どうやって管理・運用されるか」という仕組みです。
たとえば、
・生命保険信託を使って毎月一定額が支給されるようにする
・障害者扶養共済制度を活用して、親の死後も年金形式でお金が支給されるようにする
・家族信託で信頼できる兄弟や親族が財産を管理する
といった形で、資産が「安心して長く続く仕組み」を整えることが最大の備えになります。
専門家に相談するタイミング
障害者支援や相続・信託は制度が複雑で、自治体や金融機関でも理解にばらつきがあります。
そのため、次のような段階で専門家(FP・弁護士・司法書士・社会福祉士など)に相談することをおすすめします。
・障害年金の申請を検討するとき
・成年後見制度や遺言を考え始めたとき
・家族信託・特定贈与信託の活用を検討するとき
・グループホームなど将来の住まいを探すとき
一度にすべてを整える必要はありません。
「できるところから少しずつ仕組みを作る」ことが家族の安心につながります。
【まとめ】子どもの未来を「制度とお金の仕組み」で守る
障害のある子どもの将来を守るためには愛情だけでなく「制度とお金の知識」が不可欠です。
親亡き後も安心して暮らせるようにするには、
①公的制度(年金・手当・医療助成など)を最大限活用
②成年後見・遺言・信託を早めに設計
③家族で情報共有と役割分担を明確化
この3点を意識することが大切です。
「子どもを支える仕組み」を整えることは親の安心だけでなく、子どもの尊厳ある人生を守ることにもつながります。