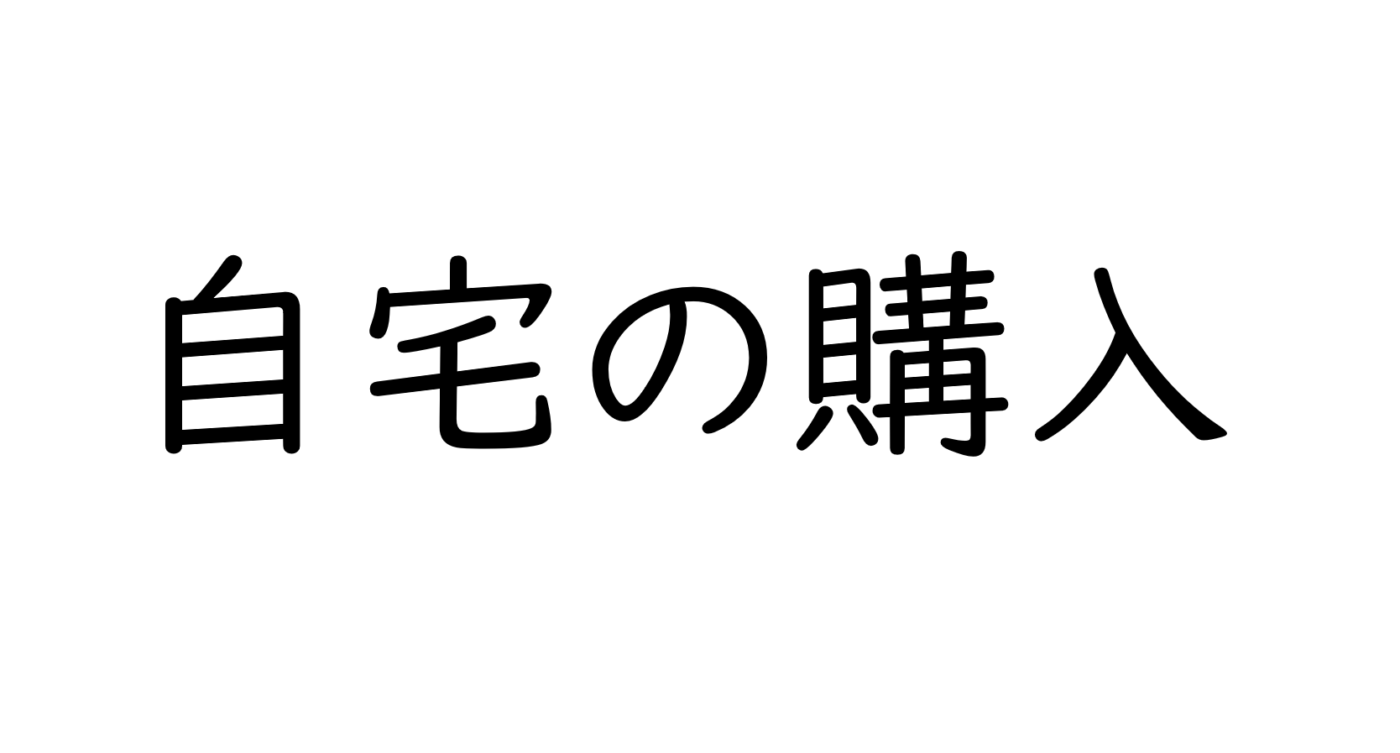誰もが一度は迷う「賃貸か?持ち家か?」
「賃貸と持ち家、どちらが得ですか?」
これは住宅相談で最も多く寄せられる質問のひとつです。
SNSやニュースでは、「今は賃貸が得」「金利が低いうちに買うべき」など、真逆の意見が飛び交います。
しかし、ファイナンシャルプランナーの視点から見ると「どちらが得か」は単純な損得計算ではなく、
ライフプラン・資産・心理的価値の3つの要素で考える必要があります。
本コラムでは「数字」と「人生設計」の両面から賃貸と持ち家の最適な選び方を解説します。
1. 「賃貸 vs 持ち家」論争が終わらない理由
このテーマが長年議論される背景には、以下のような「価値観の違い」があります。
-
賃貸派の主張:「身軽に生きたい」「ライフステージに合わせて住み替えたい」
-
持ち家派の主張:「老後の安心」「家賃を払い続けても資産にならない」
つまり、どちらが得かは「金銭面の比較」だけでは決められません。
大切なのは「自分の人生でどんな暮らし方をしたいか」という価値観を前提に数字を整理することです。
2. コストで比較する~「総支出」で見るとどう違う?~
【賃貸の例】
月12万円の家賃で30年間暮らす場合
→ 支出総額は 12万円 × 12か月 × 30年 = 4,320万円
【持ち家の例】
4,000万円の物件を頭金500万円+35年ローンで購入(金利1%)
→ 総支払いは 約4,500万円(ローン利息含む)+固定資産税・修繕費 約700万円
= 実質約5,200万円
数字だけ見れば「賃貸の方が安い」と感じるかもしれません。
しかし、持ち家の場合はローン完済後は「住居費ゼロ」になるのに対して賃貸は一生家賃を支払い続けます。
老後の年金生活を考えると、住居費の有無が生活の安定度を大きく左右します。
3. 賃貸のメリット・デメリットを整理
メリット
-
柔軟性が高い:転勤・結婚・子どもの独立など、ライフステージに合わせて住み替え可能。
-
修繕・税金の負担がない:建物管理やリフォーム費用はオーナー負担。
-
初期費用が安い:頭金不要で、引越しも比較的気軽。
デメリット
-
家賃を払い続けても資産にならない。
-
更新料や引越し費用などの「隠れコスト」が積み上がる。
-
老後の入居リスク:高齢者の入居を断る賃貸物件が多く、老後の住まい確保が課題。
4. 持ち家のメリット・デメリットを整理
メリット
-
資産になる:完済後は自分の財産。売却・賃貸・相続など活用の自由度が高い。
-
住宅ローン控除や補助金制度の活用が可能。
-
心理的な安心感:自分の家という拠点があることで家族の安定や満足度が高まる。
デメリット
-
固定資産税・修繕費などの維持コストが発生。
-
転勤・家族が増えるといったライフイベント時の柔軟性が低い。
-
住宅価格下落リスク:立地や景気により資産価値が下がる可能性。
5. FPが教える「損得の正しい見方」~キャッシュフローと資産価値~
ファイナンシャルプランナーは単に「支出額」ではなく、キャッシュフロー+純資産の変化で比較します。
(1)賃貸の場合
支出=家賃のみ。資産は残らない。
→ 30年後の純資産=「0円」
(2)持ち家の場合
支出=ローン+維持費。ただし「住宅資産」が残る。
→ 30年後の純資産=「住宅評価額 − 残債」
例えば、
・4,000万円で購入した家が30年後に2,000万円で売れる
・ローン残高が0円(完済)
であれば純資産2,000万円が残ります。
つまり、支出額が賃貸より多くても、資産が残る分だけ「結果的に得」になる可能性があるのです。
6. ライフステージ別「おすすめの選択」
① 20代:柔軟性を優先し、まずは賃貸で「暮らし方の基準」を知る
仕事や結婚、子どもの有無など変化が多い時期です。
「どんな生活をしたいか」がまだ定まらない段階では無理に購入するより家に縛られない賃貸が合理的です。
ただし、ある程度の未来予想図が描けている場合には購入しても問題ありません。
② 30〜40代:安定期に入り、教育・老後を見据えた持ち家検討期
収入・勤務地・家族構成が安定し始めたら、住宅を「資産」として組み込む段階です。
ローン控除や金利優遇を最大限活用して無理のない返済比率で購入を検討しましょう。
③ 50代以降:老後資金とのバランスがカギ
ローン完済年齢・年金受給開始時期を意識する必要があります。
持ち家の場合は売却・賃貸・リバースモーゲージなど、資産を「取り崩す」選択肢も検討しましょう。
賃貸なら老後に備え「保証人制度」や「高齢者向け住宅」も視野に入れておくべきです。
7. 「どちらが得か」を決める3つの質問
最終的に「答え」を導くには、以下の3つの質問に自分で答えてみてください。
-
今の生活にどれだけの柔軟性が必要か?
→ 転勤・転職・家族構成の変化が多い人は賃貸が向く。 -
老後に「家賃」を払い続けられるか?
→ 年金収入だけで生活を維持するには持ち家のほうが安心。 -
資産形成の視点を持っているか?
→ 住宅を「消費」でなく「投資」ととらえ、価値が下がりにくい立地を選べば持ち家が有利。
8. FPが推奨する「バランス型の考え方」
実は、賃貸と持ち家を二者択一で考える必要はありません。
例えば
①若いうちは「賃貸」で身軽に生活
②子どもができて生活基盤が固まったら「持ち家」を購入
③老後は「持ち家を売却→賃貸へ戻る」
というライフステージに応じたハイブリッド戦略も選択肢の1つです。
さらに住宅ローンを早めに完済すれば、老後は「家賃ゼロの生活」+「住宅という資産を確保」が可能になります。
9. 【まとめ】「どちらが得か」ではなく「どちらが自分に合うか」
賃貸も持ち家も「正解」は人によって異なります。
重要なのは金額の比較ではなく「人生設計」です。
・ライフプランを数値化し、キャッシュフローを可視化する
・住宅を資産として考える
・老後のリスクを見越した「住宅」を選ぶ
この3つを押さえることで、あなたにとっての「最適な住まい方」が見えてきます。
住宅は「最大の支出」ではなく「未来への投資」です。
自分と家族の理想の暮らし方を起点に、納得できる選択をしていきましょう。