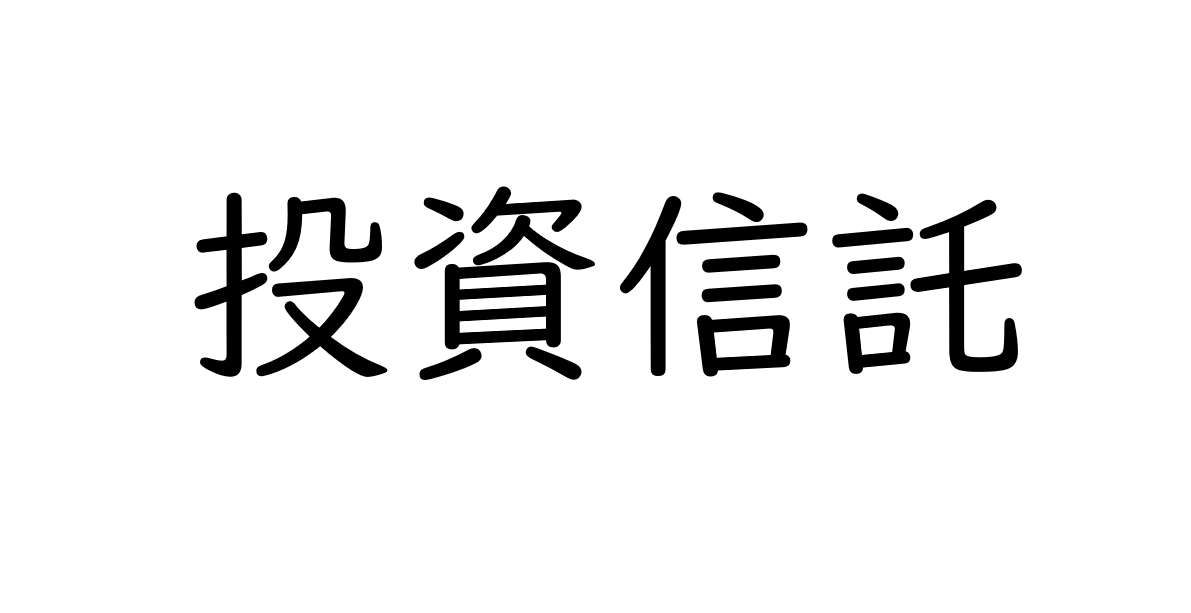iDeCo・NISAは「老後のため」の制度
iDeCo(個人型確定拠出年金)やNISA(少額投資非課税制度)は、投資で得た利益に税金がかからないという大きなメリットがあります。
ただし、iDeCoは老後まで途中解約ができない仕組みになっています。
つまり「長期の資産形成を促すための制度」であり、リターンの大きい運用商品を選ぶことでメリットを最大限活かせる設計になっています。
しかし「安全そうだから」「リスクを取りたくないから」といった理由で「債券型の投資信託」を選ぶ人が少なくありません。
リスクを抑えることは重要ですが、その選択は制度の特性をまったく活かせていないのです。
iDeCo・NISAの本質は「非課税メリットの最大化」
通常、投資で利益を得ると約20%の税金(源泉分離課税)がかかります。
たとえば100万円の投資で20万円の利益が出た場合、約4万円は税金で引かれる計算です。
ところがiDeCoやNISAでは、この税金がゼロになります。
つまり、「利益が大きければ大きいほど恩恵が大きい」のが非課税制度の特徴です。
ところが債券のように利回りが低い商品を選んでしまうと、そもそも利益が少ないため非課税の恩恵がほとんど得られません。
税制優遇を最大限に活かすためには株式型の投資信託など、長期でリターンが見込める資産を選ぶのが合理的なのです。
債券が投資信託の3つの落とし穴
① 元本割れのリスク「安全資産」ではない現実
債券は「元本が保証される」と思っている人が多いのですが、投資信託の債券型は元本割れする投資商品です。
金利が上昇すると債券価格は下落します。
たとえば金利が1%から2%に上がると債券の価値は下落します。
特に2023〜2025年にかけては世界的な金利上昇局面でした。
低金利時代に買った債券ファンドの評価額が大きく下がり「値動きが少ないから安全」と思っていた人たちにとっては大きな痛手となりました。
② 手数料負け「低リターン商品に高コストは致命的」
債券ファンドの利回りは一般的に年1〜2%前後です。
一方、iDeCoやNISAで運用する場合には信託報酬(運用管理手数料)が0.2〜0.8%ほどかかります。
さらにiDeCoでは口座管理手数料(月額約100〜500円)が毎月引かれます。
そのため利回りが低い債券ファンドでは、手数料でリターンがほとんど消えてしまうのです。
特にiDeCoは途中解約ができないため、長期的に見て「手数料負け」するリスクが高くなります。
例:年利1.5%程度の債券ファンド
手数料0.5%・口座管理費0.2% → 実質利回り0.8%程度
→ インフレ率2%だと実質マイナス運用
③ 為替リスク・信用リスク「外債ファンドの罠」
「国内債券はリターンが低いから、外国債券で運用しよう」と考える人もいます。
しかし、外債ファンドには為替変動リスクと国の信用リスクが付きまといます。
為替が円高に振れれば外貨建ての資産価値は下がります。
また、新興国債券などは利回りが高く見えても経済不安や政情リスクで大幅下落することも珍しくありません。
直接、国内の「債券」へ投資すれば価格変動リスクや為替変動リスクを回避できますが、言葉は同じ『債券』でも注意が必要です。
iDeCo・NISAでは「リスクを取る」ことがリスク回避になる
iDeCoやNISAの最大のメリットは長期運用+非課税という組み合わせができることです。
時間を味方につければ短期的な値動きのリスクは平準化され、むしろリスク資産のほうが堅実な結果を出しやすいのです。
以下は、30年間の想定リターンの比較です。
| 資産クラス | 平均利回り | 税引後実質利回り(課税口座) | 税引き前と税引き後の差 |
|---|---|---|---|
| 国内債券 | 1.0% | 約0.8% | 約0.2% |
| 海外債券 | 3.0% | 約2.4% | 約0.6% |
| 国内株式 | 6.0% | 約5.0% | 約1.0% |
| 海外株式 | 8.0% | 約6.4% | 約1.6% |
非課税制度では「低リターン商品を選ぶ=制度の旨味を無駄にする」ことを意味します。
債券型の投資信託を選んでしまうと、そのポテンシャルを自ら手放す結果になります。
これらの理由から、リスクを抑えたい場合はiDeCoやNISAを利用せずに直接「債券」を購入することをお勧めします。
安全に運用したいなら「分散と時間」を味方にする
もちろん「株式は怖い」「値動きが大きいのは不安」という気持ちも理解できます。
しかし、iDeCoやNISAは長期運用が前提です。10年以上のスパンで見れば株式市場は過去のデータ上、下落よりも上昇する期間のほうが圧倒的に長いのです。
そこで重要になるのが次の2点です。
①分散投資
株式や投資信託以外の投資、例えば債券や不動産、金などの資産にも投資することでリスクを軽減する。
②時間分散(積立投資)
毎月一定額を積み立てる「ドルコスト平均法」を活用すれば価格変動リスクを抑えながら購入単価を平均化できます。
結果的に、暴落時も安く買えるチャンスに変わります。
老後に向けた資金形成で債券が適するのは「出口戦略」だけ
債券の出番がまったくないわけではありません。
実は運用後半、老後の「取り崩し」のタイミングにこそ債券が有効です。
①60代以降で生活費の一部を安定的に補いたい
②株式の値下がりリスクを抑えたい
といった局面では債券を「守りの資産」として組み込む意味があります。
逆に、資産を増やす段階(現役期〜50代)で債券を多く持つのは非効率です。
「iDeCoやNISAで債券を買う=非課税の恩恵を放棄する」と心得ましょう。
制度を活かすなら「攻める勇気」を持つ
iDeCoやNISAは単なる貯金代わりではなく「長期・積立・分散で資産を育てる仕組み」です。
元本割れを恐れて債券を選ぶと手数料負けやインフレ負けを起こし、結果的に老後資金が足りなくなります。
制度の本質は「リスクを取らないこと」ではなく「時間を味方にしてリスクを活かすこと」です。
NISA・iDeCoでは成長性のある株式型インデックスファンドを中心に少額でも“攻めの資産形成”を始めることが賢明です。
「安全第一」のつもりが逆に危険な選択になることもあります。
このことを頭の片隅に置きつつ、「安心できる老後」の資産を手に入れましょう。