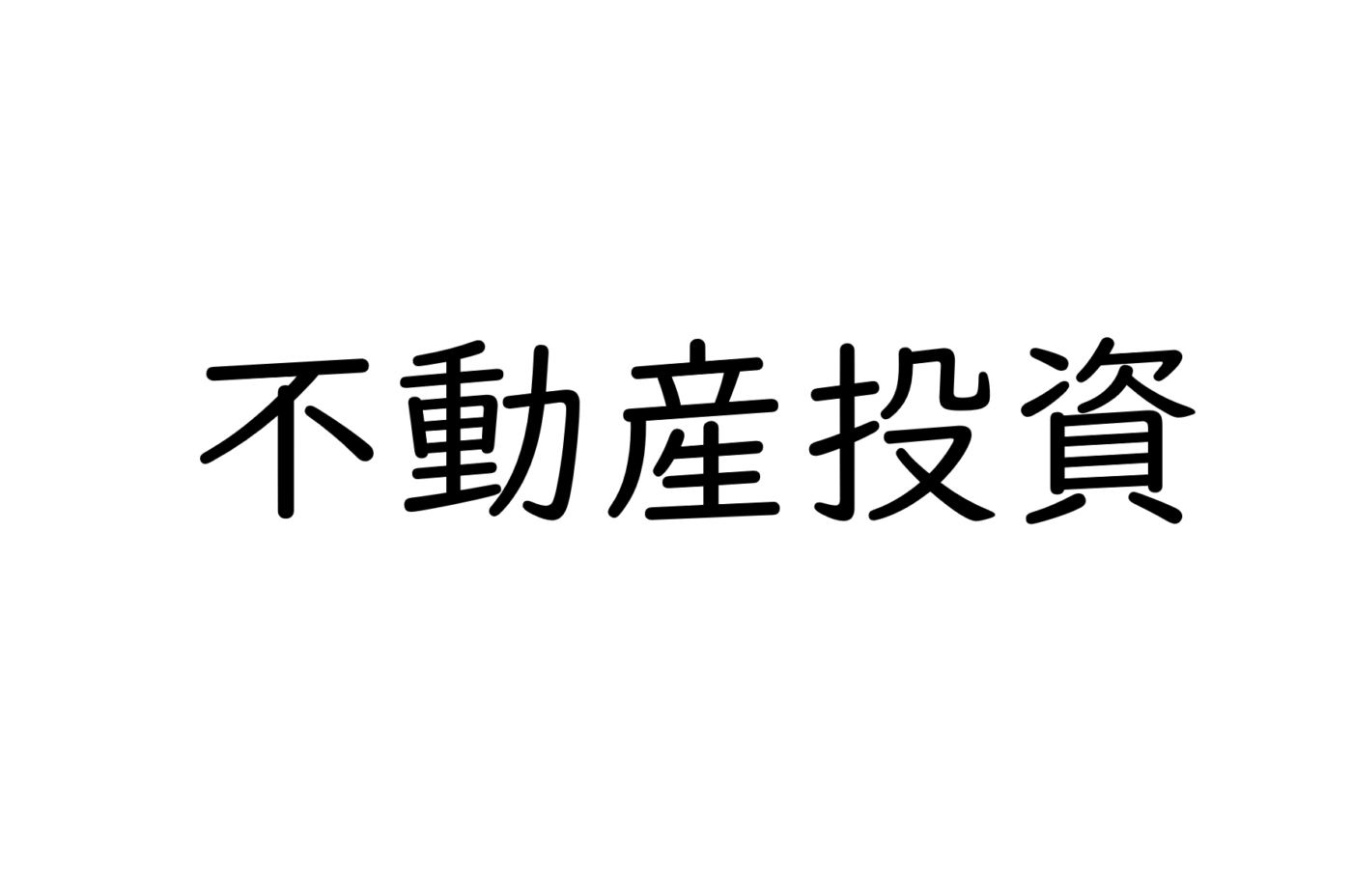【地方都市への投資が再び注目される理由】
近年、日本の不動産市場で静かに脚光を浴びているのが「地方都市物件」です。
一時は「人口減少で資産価値が下がる」「借り手が見つからない」などの理由から敬遠されがちでした。
しかし最近ではその見方が少しずつ変わり始めています。
その背景には三つの大きな流れがあります。
第一に、東京での不動産価格高騰です。
新築マンション価格は都心部で平均1億円に迫り、投資利回りは3%を下回る物件も珍しくありません。
その結果、資金効率を重視する投資家が地方都市へと目を向けています。
第二に、地方中核都市の再開発とインフラ整備の進展です。
大阪や神戸などでは、駅周辺の再開発や地下鉄延伸、オフィス需要の拡大が進み、都市機能の向上が資産価値を押し上げています。
第三に、リモートワーク・地方移住の定着です。
働く場所に縛られないライフスタイルが広がり、物価の安い地方に拠点を持つ人が増えました。
こうした「居住ニーズの分散」が地方都市の賃貸市場を再評価させています。
このように地方の不動産投資は「安いから買う」ではなく、「成長ポテンシャルを見極めて買う」時代へと変化しています。
【今後の地方不動産市場の予測と有望エリア】
では、今後の地方市場はどのように動くのでしょうか。
国土交通省の地価公示データをみると、2025年時点で全国平均は横ばい傾向ですが、地方中核都市(人口50万人以上)ではプラス圏を維持しています。
特に地価上昇が顕著な都市としては、以下のエリアが注目されています。
大阪市:再開発が進む「西日本経済の中心地」
大阪市は関西圏最大の経済都市であり、再開発による地価上昇が続くエリアです。特に梅田の「グラングリーン大阪」や「なんばパークス南再開発」、2025年大阪・関西万博後のIR(統合型リゾート)構想など、都市機能の拡張が進行中です。企業・観光・学生と多層的な人口が集まるため、単身向けからファミリータイプまで賃貸需要が豊富。交通利便性が高く、管理運営もしやすいことから、安定したキャッシュフローを狙える都市として注目されています。
京都市:観光・文化が支える「インバウンド型安定市場」
京都市は歴史と文化が融合した国際観光都市であり、ホテル・民泊・レジデンス投資が盛んな地域です。特に東山区・中京区・下京区では観光需要が安定しており、円安の影響で外国人観光客が急増。住宅系では学生・観光関連従業員・単身赴任層の需要も底堅いです。一方で、景観条例や建築制限が厳しく、新規供給が抑制されているため、既存物件の希少性が資産価値を支えています。中長期的に“供給制約による価格維持”が期待できるエリアです。
神戸市:住環境と安定需要が魅力の「成熟型都市」
神戸市は海と山に囲まれた住環境の良さが評価され、ファミリー層や医療関係者の定住需要が高い都市です。三宮駅周辺では再開発「三宮クロススクエア計画」が進行し、商業・オフィス・住宅が融合する新都心構想が現実味を帯びています。大阪・京都へのアクセスも良好で、賃貸ニーズは安定。大幅な地価上昇は見込みにくい一方、賃料変動が小さく、長期保有で堅実なリターンを得たい投資家に向いています。安定志向の地方投資の代表格といえるでしょう。
福岡市:九州経済の中心。
空港・博多駅・天神のアクセスが良く、再開発(天神ビッグバン)が進行中。単身者・法人需要ともに旺盛。
札幌市:観光・IT関連企業の進出が続き、賃貸需要が底堅い。
インバウンド回復でホテル・民泊需要も上向き。
将来的にも賃貸需要が途切れにくく、売却時の出口戦略も立てやすいという特徴があります。
一方、地方の中でも「人口10万人未満のエリア」では空き家率が上昇しており、投資先としては慎重な見極めが必要です。
今後は「地方=リスク」ではなく、「どの地方都市が成長できるか」を見極める眼が試される時代と言えます。
【成功パターンと失敗パターンの分岐点】
地方都市物件で成功している投資家には、いくつかの共通点があります。
成功パターンの特徴
1エリア選定を「人口動態」で判断する
単に地価や家賃水準だけでなく、5年・10年単位の人口推移、特に20〜40代の流入・流出を確認する。
2需要を見据えた物件タイプの選定
単身者向けワンルームだけでなく、「リモートワーク対応1LDK」「駐車場付き2LDK」など、地域特性に合わせた設計を重視する。
札幌などでは冬場の光熱費を抑える断熱仕様が差別化要因になります。
3地元管理会社との連携強化
地方では「管理の質」が成否を分けます。
地域密着の管理会社は家賃設定・リフォーム提案・入居者対応に精通しており、空室リスクを最小化できます。
4出口戦略を初期段階から設計する
「10年後に売却して利確する」のか「家賃収入で20年以上保有する」か、ゴール設定を明確にすることで利回り・修繕・融資計画を合理的に立てられます。
失敗パターンの典型例
1地元の不動産会社に「利回り8%」と勧められて築古物件を購入するも、実際は修繕費と空室で赤字化。
2地方銀行から融資がつくからと購入するが将来的に売却先が限られて出口(売却)で詰まる。
3地方移住ブームを過信してリゾート地の物件を購入。しかし需要が一時的で家賃下落してしまう。
つまり「高利回り」に飛びつくのではなく、「安定的に貸せる構造」を持つかどうかが最大の分岐点になります。
【「安く買う」より「賃貸需要を読む」時代へ】
これから先、地方の不動産市場は「二極化」が進むと予想されます。
成長する地方都市は地価上昇・再開発・企業進出が重なり、安定的なキャッシュフローが期待できます。
一方で人口減少が進むエリアでは空室率上昇・家賃下落が続き、資産価値の維持が難しくなるでしょう。
初心者にとっての戦略は「地方だから安い」「東京が高いから地方」という短絡的な発想ではなく『その都市が10年後も“選ばれる街”であるか』を見極める力を養うことです。
実際に物件を選ぶ際には、
・市の人口統計(特に20〜40代の推移)
・大学・企業・再開発の動き
・賃貸サイトでの空室率・家賃相場
などを自分でリサーチする習慣を持ちましょう。
地方物件投資は「手間がかかる分、情報格差で差をつけやすい」市場です。
地元企業とのネットワークや管理会社との信頼関係を構築できれば、東京では得られない高利回り・安定収益を実現できます。
そして、投資家にとって最も大切なのは「焦らないこと」です。
地方投資は一発勝負ではなく地域とともに育てる長期戦略です。
人口減少が続く日本であっても都市間には明確な成長格差があります。
その中で「未来に人が集まる場所」を選び、丁寧に運用していくことが大切です。
それがこれからの時代における地方不動産投資の成功パターンと言えます。