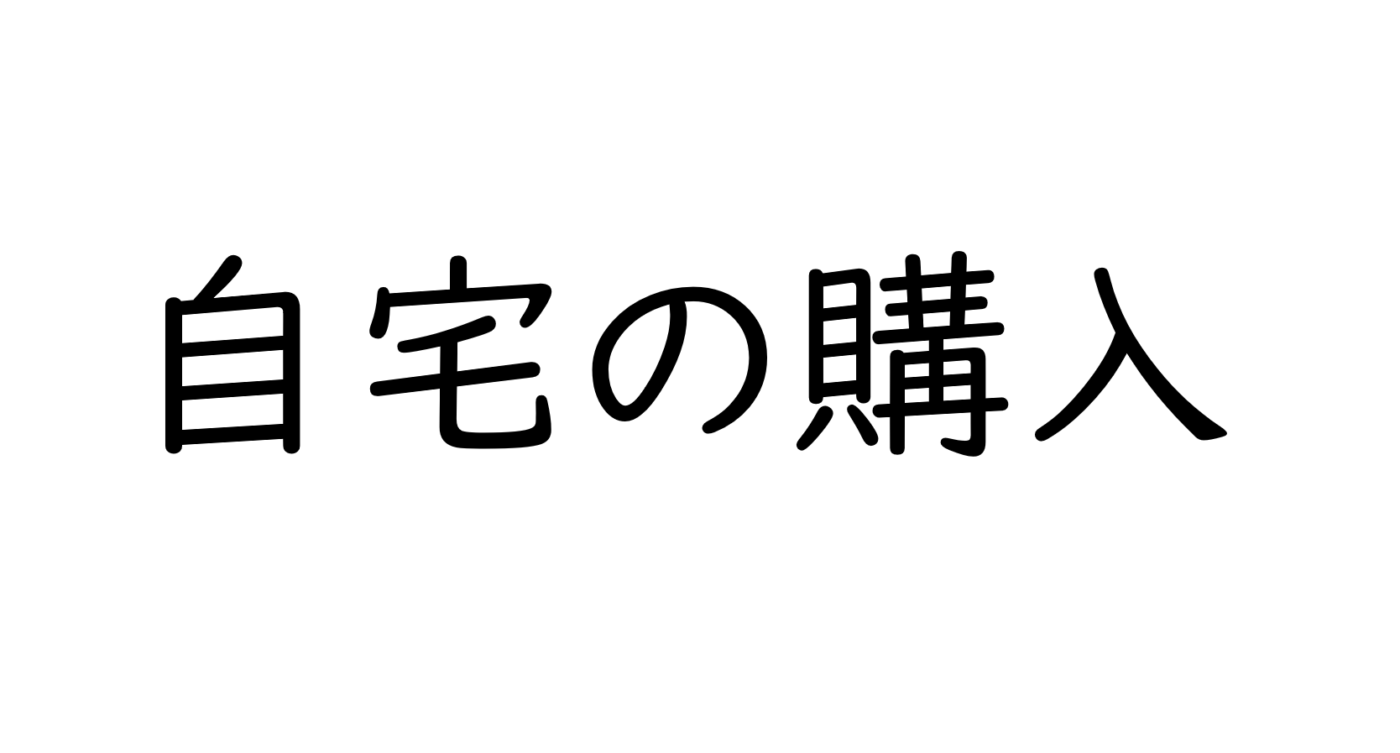住宅ローンの「選び方」で数百万円の差が出る
住宅購入において多くの人が注目するのは「物件の価格」です。
しかし「住宅ローンの組み方」が将来の家計を大きく左右します。
金利タイプ・返済期間・ボーナス併用・繰上げ返済など。
こうした選択肢を正しく理解しないまま契約してしまうと結果的に数百万円の差が生まれることも少なくありません。
本コラムではファイナンシャルプランナーの視点から、
住宅ローンに潜む「5つの落とし穴」と、その回避法を具体的に解説します。
1. 落とし穴①:「金利タイプ」を「金額の安さ」だけで選ぶ
住宅ローンには主に3つの金利タイプがあります。
| タイプ | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 固定金利型 | 返済終了まで金利が一定 | 返済額が安定・安心 | 金利が高めに設定される |
| 変動金利型 | 半年ごとに金利が見直される | 初期金利が低く、返済額が少ない | 将来、金利上昇のリスク |
| 固定期間選択型 | 5年・10年など一定期間固定 | 一定期間は安定、終了後は再選択可 | 再設定時に金利上昇の可能性 |
一見、「変動金利」は金利が低くお得に見えます。
しかし金利上昇局面では返済額が増加して家計を圧迫する可能性があります。
たとえば、金利0.5%が1.5%に上がるだけで、月々の返済が約2万円増えるケースもあります。
つまり、「今の金利」だけで判断するのは危険です。
大切なのは、「金利が上がったときに支払いが維持できるか」を事前にシミュレーションすることです。
そのため、手元に預貯金がしっかりあれば変動金利で返済額が上昇しても繰上返済するなど対処可能です。
2. 落とし穴②:「返済期間を長くすれば安心」と思い込む
多くの人が「35年ローンで月々の負担を抑えよう」と考えます。
しかし、返済期間を長く設定すると支払総額が大きく膨らむことになります。
例:3,500万円を金利1%で
-
35年ローン → 総返済額 約4,030万円
-
25年ローン → 総返済額 約3,705万円
つまり、期間を10年短縮するだけで約325万円の節約が可能です。
「返済期間が長い」=「支払総額の増加」と理解した上で、
余裕があるうちは繰上げ返済で期間短縮を狙うことが長期的な家計防衛になります。
ただし、資産運用の理解のある世帯であれば金利の低い住宅ローン返済に資金を振り向けるのではなく、
ある程度の利回りがあって安定した金融商品へ資金を入れた方が将来の資産は増加します。
3. 落とし穴③:「ボーナス返済」を当てにしてしまう
住宅ローンの返済方法として、「ボーナス併用払い」があります。
ボーナス月に多く返済することで月々の返済額を抑える仕組みです。
しかし、これは景気や勤務先の業績に左右されやすく将来の不安定要因になります。
近年は「ボーナスが減額・カット」される企業もあります。
仮にボーナスが減った場合、返済計画が一気に崩れ、延滞・リスケジュール(返済条件見直し)のリスクも。
ファイナンシャルプランナーとしての原則は明確です。
「ボーナスは繰上返済に充てるものであり、毎年の返済に組み込むものではない」
月々の収入(給与)だけで完済できる返済設計にすることが安全なローン組みの基本です。
4. 落とし穴④:「団信(団体信用生命保険)」の中身を理解していない
住宅ローン契約時に付帯される「団体信用生命保険(団信)」は、
契約者が死亡または高度障害になった場合にローン残債が0円になる保険制度です。
しかし、団信の内容は金融機関によって異なります。
近年では、以下のような「付加型団信」も登場しています。
| タイプ | 補償内容 |
|---|---|
| がん団信 | がん診断時にローン残高が半額または全額免除 |
| 生活習慣病団信 | 3大疾病や就業不能時も補償対象 |
| 精神疾病団信 | 精神疾患・うつ病などにも対応(条件あり) |
こうした団信は保障が厚い反面、金利が上乗せされるケースがほとんどです(+0.1〜0.3%程度)。
つまり「安心感を取るか、金利負担を取るか」の判断が求められます。
「自分の家庭にどの保障が必要か」を明確にし、
既存の生命保険・医療保険との重複や無駄がないかをFPなど専門家の視点でチェックしてもらうことが大切です。
5. 落とし穴⑤:「繰上げ返済」を「勢い」で行ってしまう
繰上げ返済は利息を減らす有効な手段ですが、やり方を間違えると逆効果です。
たとえば、
-
住宅ローン控除の期間中(13年間)は繰上げ返済を控える方が得な場合もあります。
-
手元資金が減りすぎると教育費や生活防衛資金が不足し、結果的に家計が不安定になります。
正しい順序は次のとおりです。
① 生活費6か月分の預金を確保
② 教育費・老後資金の見通しを立てる
③ 控除期間後に、繰上げ返済を計画的に実行
つまり「繰上げ返済」はタイミングを見計らって実行する必要があります。
6. 【FPが提案】損しないための「返済戦略」3ステップ
ステップ①:返済比率を30%以下に抑える
月々の返済は「手取り月収の30%以内」に収めること。
これを超えると教育費・老後資金の余力がなくなります。
ステップ②:ライフプランを基にシミュレーション
住宅購入は「ゴール」ではなく「スタート」。
結婚・子ども・転職・介護など人生イベントごとにキャッシュフロー表を見直すことで将来の破綻リスクを下げられます。
ステップ③:固定+変動の「ミックスローン」を検討
金利上昇リスクを抑えつつ低金利の恩恵を得たい場合、
一部を固定・一部を変動で組み合わせる「ミックスローン」も有効です。
リスク分散の視点から見ても安定した選択といえます。
7. まとめ:「住宅ローン=長期の資金戦略」で考える
住宅ローンの失敗は「目先の金利」にとらわれすぎた結果です。
本来、ローンは「35年間の長期にわたる資金戦略」であり、
「金利」「期間」「保障」「繰上げ返済」の4つを一体で考えることが重要です。
落とし穴を避けるポイントを整理すると、
-
金利タイプは「余剰資金の有無」で選ぶ
-
返済期間は余裕があれば「短縮」する
-
ボーナス返済に頼らない
-
団信内容を理解し、保険の重複を避ける
-
繰上げ返済はタイミングを見極める
住宅ローンは「借金」ではなく、「人生のキャッシュフローを最適化する道具」です。
家を買う前に、これらのポイントを押さえておけば、
ローンに振り回されることなく、家計の自由と安心を手にすることができます。
また「住宅の購入価格を抑えたい」「現状で自宅を購入しても問題ないか?」など気になる事があればお問い合わせフォームよりご連絡ください。⇓⇓